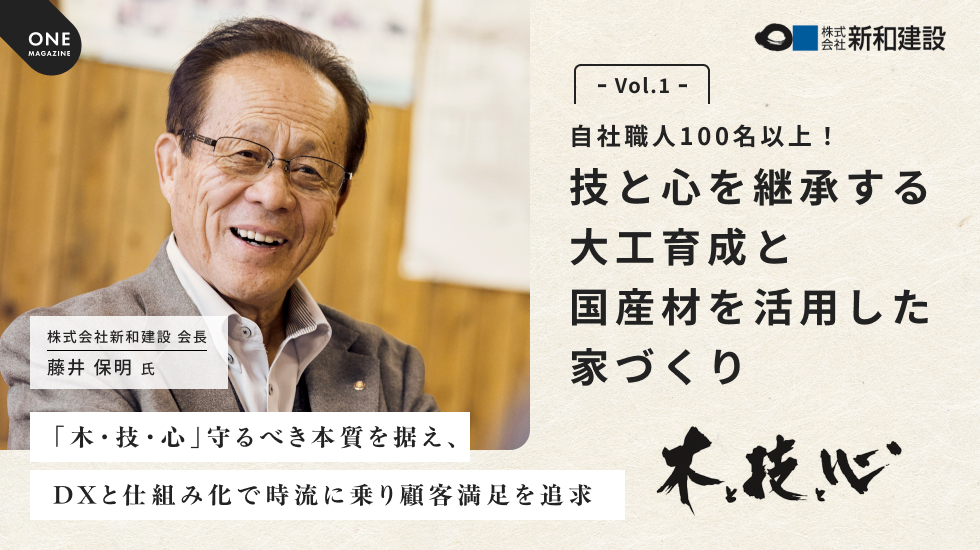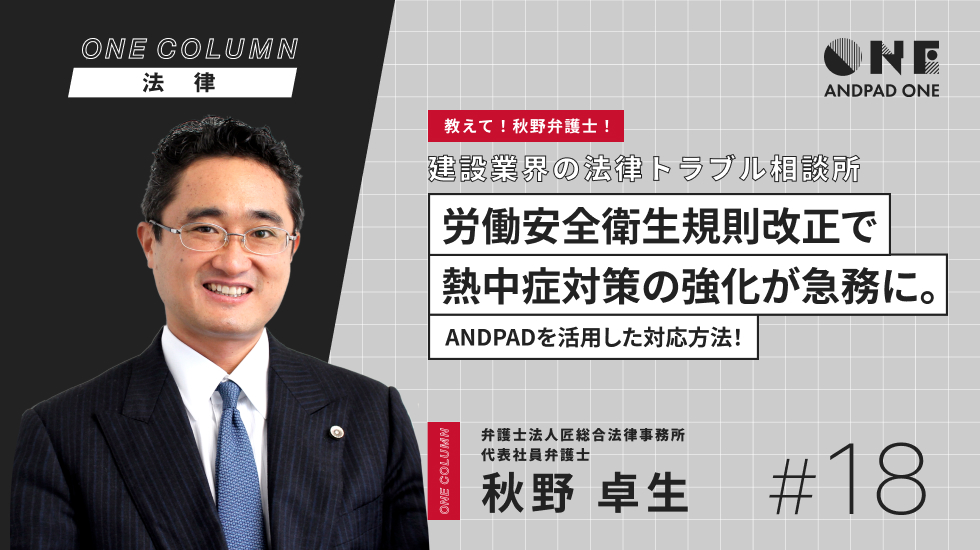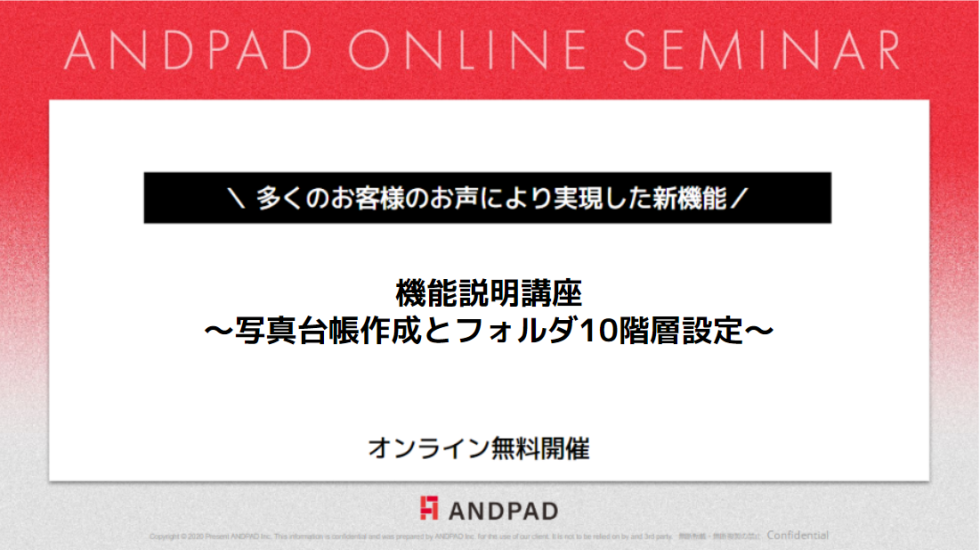目次
2023年7月、熊本県山鹿市の静かな山間に、新たな建設業の働き方を提唱する革新的なオフィスが誕生しました。それが、株式会社Lib Workが廃校をリノベーションした「Lib Work Lab(リブワークラボ)」です。
株式会社Lib Workは、福岡・佐賀・大分・千葉・神奈川などで事業を展開する上場住宅メーカーです。同社は、「サステナブルとテクノロジーで住まいにイノベーションを起こす」ことをミッションに掲げています。同社は実際、CG・VRを活用して初期設計のプラン提案を行うサブスク事業「マイホームロボ」や、著名なライフスタイルブランドとのコラボレーションを行うIPライセンス事業など、常識にとらわれない新たな手法に挑戦し続けています。
Lib Work Labはそんな同社を象徴する場所。かつての学び舎は、社員一人ひとりのクリエイティビティと自発性を育む拠点として、新たな命を吹き込まれました。この場所は、オフィスが手狭になったという切実な課題を解決しただけではありません。社員のコミュニケーションを活性化し、より働きやすい環境を構築するという同社の強い意思が形になった場所なのです。なぜ同社は、廃校活用というユニークな選択をしたのでしょうか。そして、この場所でどのように新たな価値が生まれているのでしょうか。
今回は、本リノベーションプロジェクトを担当した建築部次長 工程コスト管理課 課長の山田亜都幸さんと、営業部 設計課 課長の永野真史さんに、コミュニティマネジャーの平賀が、お話を伺いました。
3階建ての廃校を活用しフルリノベーションしたLib Work Lab
Lib Work Lab(リブワークラボ)は2017年3月に閉校になった3階建て小学校をフルリノベーションした、Lib Workの第二の本社オフィスです。熊本県山鹿市内にあり、同市内にある本社から車で15分と利便性も確保しながら、周辺環境は緑が多く、通勤時には人の流れと逆走するために渋滞に巻き込まれないという好立地にあります。

Lib Work Lab 正面入口には、社名サインがあしらわれている(写真左)。緑に溢れたLib Work Lab周辺環境(写真右)。
校舎だった延床面積1725.28平米の敷地はフル活用されています。まず大小8つのミーティング室で、気軽に従業員同士でディスカッションできる環境にしたほか、リモートワークなどの多様な働き方をする従業員のためにWeb会議専用ルームを4室、「集中スペース」として半個室のデスクも5台設置し、思考の拡散と集中の両方を達成できる空間になっています。

元教室を活かした開放的な執務スペース(写真左)と、半個室の集中スペース(写真右)。
さらに、子連れ出勤をする従業員が多いことを受けて、キッズスペースや授乳室、更衣室なども確保しています。敷地内に設置した同社初となる社員食堂は、いずれは子ども食堂の運営拠点としても利用予定だといいます。
また隣接する農地も購入してアトリエを建て、素材研究や試作などR&D(Research and Development:研究開発)に活用しています。その結果、これまでは本社横の施策工房で行っていた研究開発を、広々とした場所で行えるようになりました。本記事の後編で紹介する3Dプリンターハウスも、ここで試作されています。
アンドパッド 平賀(以下、平賀): Lib Work Labに関するさまざまな記事を拝見して楽しみにしていたのですが、中に入ってみると想像以上にホッとする空間ですね。会社らしいピリッとした空気というよりも、遊び・学びの延長のような雰囲気があります。先ほどお手洗いで若い男性社員さんが歯磨きをしていらしたのを見たからか、何か合宿のような雰囲気も感じます。あの、手書きの「関係者以外立ち入り禁止」の看板は、最初からあったのでしょうか?
山田さん: いらっしゃる協力会社さんも皆さん「懐かしいな」とおっしゃるんですよ。看板はいつの日からか、できていました。社員ではない人がトイレを使っていたり、地域のおじいちゃんが2階の会議室にいたりして、さすがに最低限の仕切りは必要だと考えて作ったんですよね(笑)。

左から、山田さん、アンドパッドのコミュニティマネージャー平賀、永野さん
永野さん: 体育館は山鹿市の持ち物のままなので、イベントなどが行われることもあるんです。そうすると、子供がそのまま入ってきてしまったり、2階の元校長室をリノベーションした休憩所で知らない人が自販機で飲み物を買っていたりしていたんです。

平賀: 街にすっかり溶け込んでいるのですね。あの看板のおかげで、私も勝手に中に入らずに踏みとどまれました(笑)。
社内のコミュニケーションが円滑になる内部空間
平賀: 二宮金次郎の像が残っていたり、下駄箱がそのまま使われていたりする一方で、現代的なオフィスらしいインテリアもあって、バランスがいいですね。

写真右、1階から2階へ上がる階段の裏には、小学校にあった石がそのまま飾られている。
山田さん: 家具などはそのまま学校にあったものも多いです。下駄箱も塗装して使っています。靴を入れる位置は指定されているわけではないのですが、自然と決まってきましたね。廊下と教室の仕切り壁や、教室同士の間の壁など構造上必要ではない壁は取り払ってしまいました。朝出社するときには、さまざまな課の横を、挨拶をしながら通り過ぎて、自分の課に行くんですよ。

平賀: 小学校で挨拶が励行されているのに似た雰囲気がありますね。開所してから2024年度、2025年度と新入社員を迎えられていますが、熊本市内のサクラマチオフィスもある中で、新入社員の方はこちらに出社するのでしょうか。オフィスに緊張しながら来るのとは、まったく違う体験になりそうですね。
永野さん: 配属にもよりますが、基本はこちらです。3階に100人ほど入る集会所のような部屋があるので、そこで入社式や研修を行なっています。たしかに会社っぽくはないかもしれませんね。

平賀: オープンな環境で、学校のような和気藹々とした雰囲気があるので、リラックスできる。一方で集中環境も整っているからゾーンに入ることもできる。クリエイティビティが発揮される場所なのだろうと感じます。一方で、緊張感を高めたいとき、ピリッとした空気感を持ちたい時には支障はないのでしょうか。
山田さん: 大きな部屋と小さい部屋と様々な部屋があるので、ピリッとしたい時にはみんなで会議室に集まって一気に指示してもらったり、個人面談をしたりもできるんです。「和気藹々」だけでもないと感じています。

平賀: これだけの広さがあるからこそ、細かい空間の使い分けができるのですね。本社のオフィスにいらっしゃったときと、コミュニケーションの質は変わりましたか?
山田さん: 確実に変わったと私自身は感じています。会話の総量は大幅に増えました。本社にいる時にはどうしても周りに気兼ねをして、電話をする時にも一度外に出たりしていたんです。部屋がなさすぎて1対1の面談ができず、車の中で話すこともありました。今は個室もたくさんありますし、2人、3人、4人のミーティングもしやすくなりました。大声も出せるし、爆笑もできます。
平賀: 天井が高いからか、音の反響がうまく計算されているのか、学校という場所の特性なのかはわからないのですが、笑い声や大声がノイズにならないのが不思議ですね。

各課ごとの執務スペースの様子
平賀: 社員食堂は平日毎日稼働しているのですか?
山田さん: そうなんです。それもあって、熊本市のサクラマチオフィスに出社してもいいことにはなっているのですが、Lib Work Labの方が人気です。小鉢2つにメインと汁物とご飯が出るのですが、400円払えばあとは会社が負担してくれます。今は昼だけなのですが、夜も利用したいという声は多いですね。

社員食堂の様子。写真右、山田さんと共に写っているのは、永野五月さん。ANDPAD AWARD 2025 ユーザー部門「ベスト受発注ユーザー賞 -発注-」で3位を受賞されました。
平賀: すばらしいですね。健康寿命が伸びそうです。最低限摂取カロリーが取れるし、バランスもよいし、若手社員にとっては可処分所得も増えるありがたい取り組みですね。食事をとりながらコミュニケーションすることもできそうです。
永野さん: 社長の瀬口も社員食堂は利用しますし、営業も毎週月曜日にいろんな営業店から人を集めてランチミーティングをしていますね。外部の方が来訪くださった時に一緒にご利用いただくこともあります。
平賀: Lib Work Labはどうしたら働きやすいか、どうしたらコミュニケーションが増えるのかを、よく考えて作られているのですね。
キャリアを途切れさせない工夫、長く働ける環境を構築
平賀: 子連れ出社が多いということをお聞きしましたが、食堂で皆さんのご家族が利用することもあるのですか?
山田さん: よくあります。永野さんのような社内結婚組のお子さんたちはもちろん、全社員約300名のうち子連れ社員が半数くらいはいるので、常にLabには子供がいて、食堂も利用することがあります。食堂以外でも、畳敷きの部屋もあるので、そこで子供たちが遊んでいたりします。とくに私が勤める工程コスト管理課では多いですね。
平賀: 元は学校で、音が気になりにくい環境ではあると思うのですが、社風として、子供がいることで気が散ってしまう社員の方はいないのでしょうか。
山田さん: そういう人は、まったくいないですね。子どもと一緒にいることに、みんな慣れています。一緒に走り回ったりしている社員もいるくらいです(笑)。その結果、最近、ようやく子育てを理由に辞めないでくれる社員が増えたなと感じます。ここに託児施設があれば完璧なんですけれど。

平賀: キャリアを止めない環境を意識的に作ってらっしゃるのですね。私たちANDPAD ONEチームも子育て世代が多いですが、意欲のあるファイターが働きやすい環境を作ることは必要ですよね。
貴社ではANDPADを導入してリモート環境で仕事ができるように整えたり、コロナ禍でテレワークを導入したりするなど、様々な形では働きやすい環境つくっているのですね。しかも、会社がやってくれるのではなく、自分たちで自ら環境を作っていこうとなさっているのが特徴的だと感じます。
山田さん: 必要に迫られているところも多いと思いますけれど、環境を整えていくのは大事ですよね。

通常業務を行いながら、ANDPAD導入と並行で短工期で行った廃校活用プロジェクト
平賀: 自由で創造的な雰囲気を感じるので、Lib Work Labを作ったのは貴社にとって非常にメリットのあるものだったと予想するのですが、そもそもなぜ廃校をリノベーションすることになったのですか?
山田さん: 鍋田の本社に人が増えて手狭になったので、拠点を分散させずにみんなが集まれる場所を探していました。その時に、今は取締役になっている部長の城浩輔が「山鹿市に廃校があるね」と言い出したんです。彼はこの小学校出身なので、場所を知っていたんですよね。それで、山鹿市役所に「廃校って買えるんですか」と問い合わせました。
平賀: 市役所の担当者も驚いたでしょうね。
山田さん: 市役所の人も初めてのことだったので「ちょっと確認します」と言われました。そこで、こちらも本気度を見せねば、とプレゼンをしに行きました。
永野さん: 最終的に山鹿市が廃校の公募型プロポーザル方式で事業計画案を募ることになったんです。弊社ともう一社が提案を出したらしいのですが、コンセプトで弊社を選んでいただけました。その後、住民説明会を経て、リノベーションを進めました。

平賀: このプロジェクトのメンバーにはどんな人がアサインされたのでしょうか。専任の方はいらっしゃったんですか?
山田さん: 専任はいませんでした。当時の建築部長がリーダーとなり、私は内装や表札、照明など目に見える部分、インテリアコーディネートを担当しました。永野さんたち設計部が設計を担当して。プロジェクトチームとしては4、5名ぐらいですが、社内総出で、みんな兼務で担当しました。抜擢されたというよりも、ある日「この日までにお願い」と図面が届いて、自然にそれを考えることになっていた感じですね。

平賀: Lib Work Labは2023年7月に誕生していますよね。どのくらいの期間でできあがったのでしょうか。
山田さん: プロポーザルは2022年の末にあり、2023年の2月から解体がスタートしたんですよね。
永野さん: プロポーザルの段階である程度、基本設計をしておいて、その後12月から2月の間に実施設計を詰めていきました。そこから7月オープンなので、実質で工期は4カ月ぐらいですね。設計は、社内で何人かで手分けしてやりました。
平賀: これだけの規模で工期が4カ月というのはすごいですね。
永野さん: 空調がなかったのでダクトを通してエアコンを入れることは大掛かりでしたが、あとは壁を壊したぐらいで基本的にあるものを活用しています。壁を壊したところも色を塗っているだけです。構造は基本的にいじらず、申請が必要ない範囲でのリノベーションだったんです。
山田さん: とはいえ、報道機関を招いた開所式を7月に行うことが決まっていたので、間に合うか焦る気持ちはありましたね。プレスリリースを出してしまってから、発注し忘れていたものに気づいたり、色を決めていない部分に気づいたり。
平賀: 急ピッチでなされたのですね。しかも、その裏ではANDPAD運用浸透プロジェクトを行っていたんですよね(※)。通常業務を行いながら、ANDPAD運用のために今まで使っていたシステムや業務を変え、ワークフローを変えていただいたはずですが、それと並行してリノベーションプロジェクトも進行していたとは。それだけでも一大事で大変なところを、本当に皆さんのバイタリティには目を見張るものがあります。さらに永野さんに至っては、後ほどお話をお聞きする3DプリンターのR&D活動も並行してなさっていたんですよね。コロナ禍でもあったはずですし。
山田さん: 何かの仕事が発生したときには、みんな「はい」という返事しか持っていないんですよ(笑)。永野さんはちょうどその頃、3Dプリンターの機械の視察にヨーロッパに出張にも行っていました。
平賀: チャレンジする人を応援し、サポートする風土なんですね。ANDPADのプロジェクトには、永野さんは関わってらっしゃったのですか?
永野さん: 設計部代表としてANDPAD推進プロジェクトにも関わっていました。設計目線からここまでにこれがないとだめだ、とマイルストーンを整理したり、次のワークフローに移行するための条件設定を考えたりしていました。
(※)同社は、現場の「見える化」によってより効率的な分業化を実現するために、以前使用していた施工管理アプリからANDPADへと切り替えを行っています。それを進めたのが「ANDPAD推進プロジェクト」。ANDPADの運用浸透をボトムアップで早期実現し、働き方の多様化を実現、経験知の少ないメンバーも働ける仕組みをつくって、月706万円の労務費を削減したプロセスと成果から、ANDPAD AWARD 2023のDXカンパニー部門において、カテゴリ対象及びONE賞を受賞しています。ANDPAD推進プロジェクトの取り組みについて詳細は以下の記事からぜひご覧ください。

校内には、ANDPAD AWARD 2023 受賞トロフィーや、受賞特典『ONES』のポスターも。
平賀: 要のメンバーとしてしっかり参加されていらっしゃったんですね。新規事業プロジェクトにアサインされていらっしゃるのは、「働くこと」、それもLib Workで働くことを楽しんでいると周りの方々から認識されているからでしょうね。施工期間はすでにANDPAD導入後だと思いますが、リノベーションプロジェクトもANDPADで管理されていたのですか?
山田さん: はい、施工時には進捗報告などでさっそく活用しました。熊本市にあるサクラマチオフィスに出勤している社員でも、興味があればいつでも進捗を確認できるので便利でしたね。
永野さん: 3DプリンターハウスプロジェクトにもANDPADを活用していますよ。今は「Lib Earth House model B」(以下、「model B」)を作っているのですが、カメラを取り付けて動画を撮り、それをANDPADと連携しています。
平賀: そうでしたか! 後編では3Dプリンターハウスプロジェクトについて詳しくお聞きしたいです。

Lib Work Labを訪れお話を伺う中で見えたのは、廃校というユニークな場所が「単なるオフィス」であることを超え、社員の創意工夫と自発性を育み、活発な社内コミュニケーションを促す場として機能している、ということでした。社員のみなさんのチャレンジャー精神とバイタリティ、人柄の良さ、助け合う風土が、Lib Work Labという「場」との掛け合わせにより強固なものへつながっていることが見て取れます。
続く後編では、引き続き永野さんと山田さんに登場いただきながら、同社の「3Dプリンターハウスプロジェクト」について詳しく紹介していきます。
| URL | https://www.libwork.co.jp/ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 瀬口 力 |
| 創業 | 1997年 |
| 本社 | 〒861-0541 熊本県山鹿市鍋田178-1 |