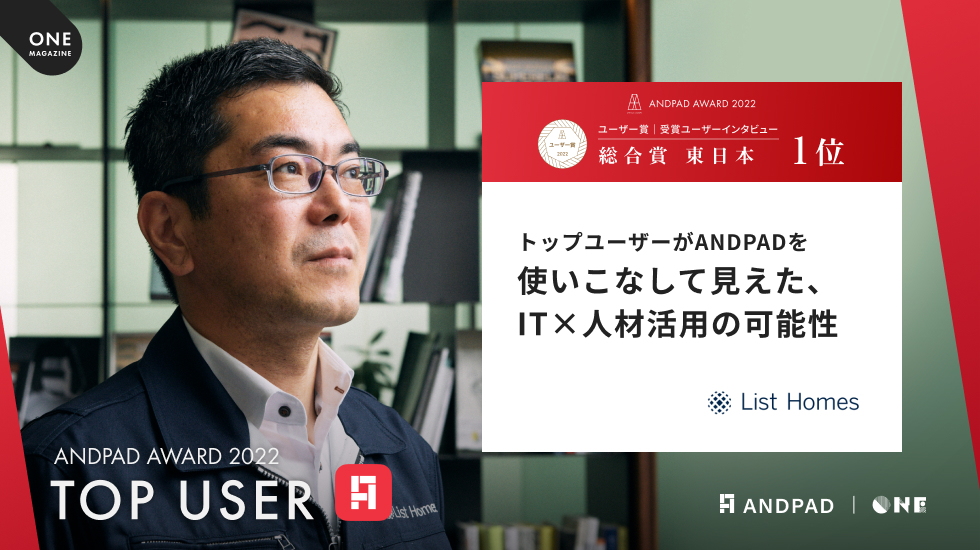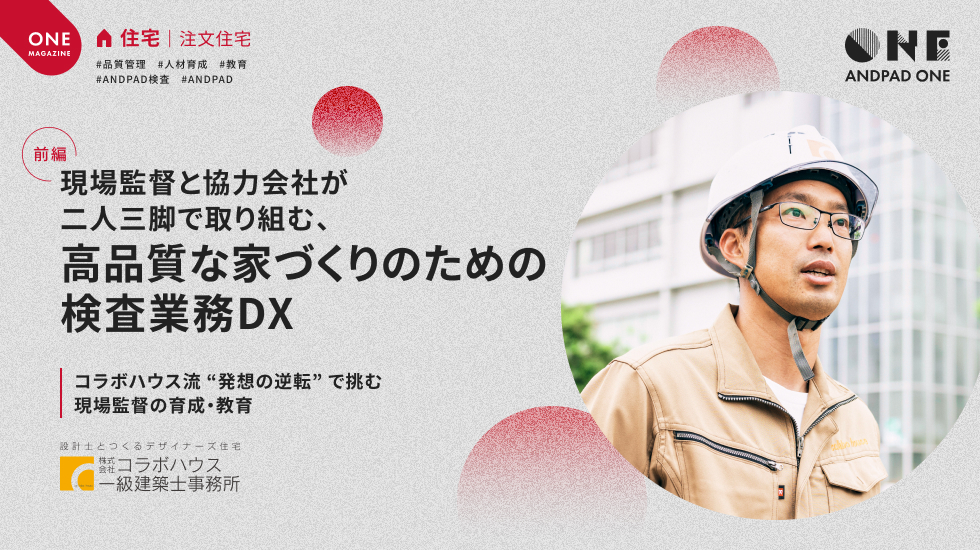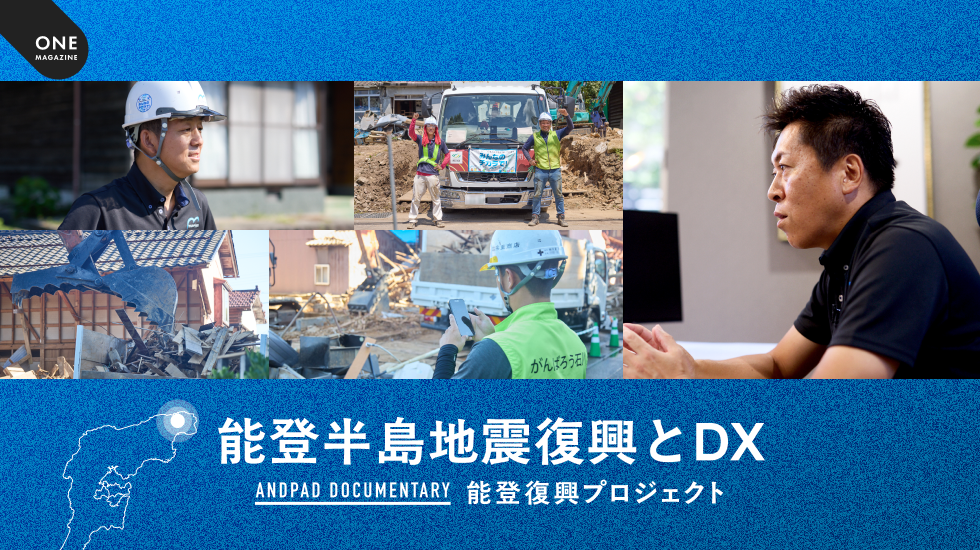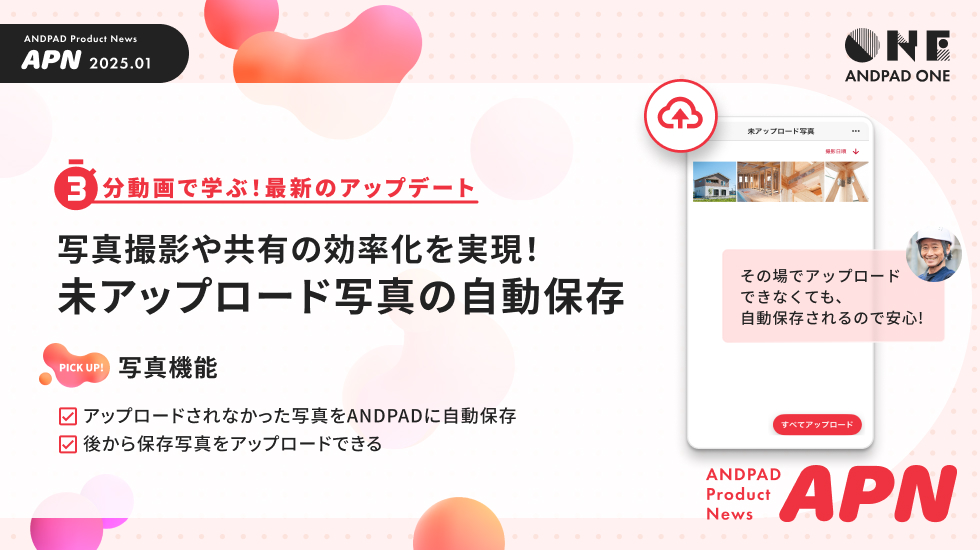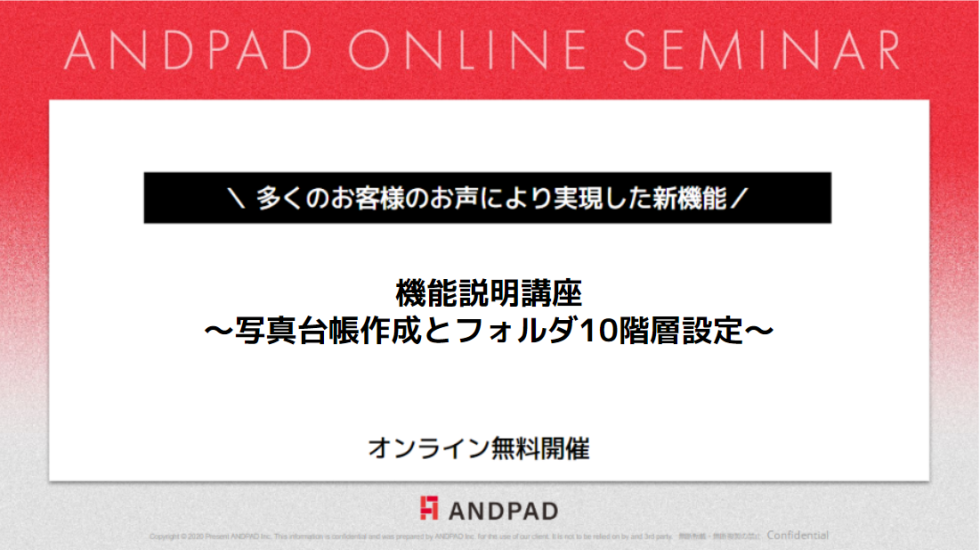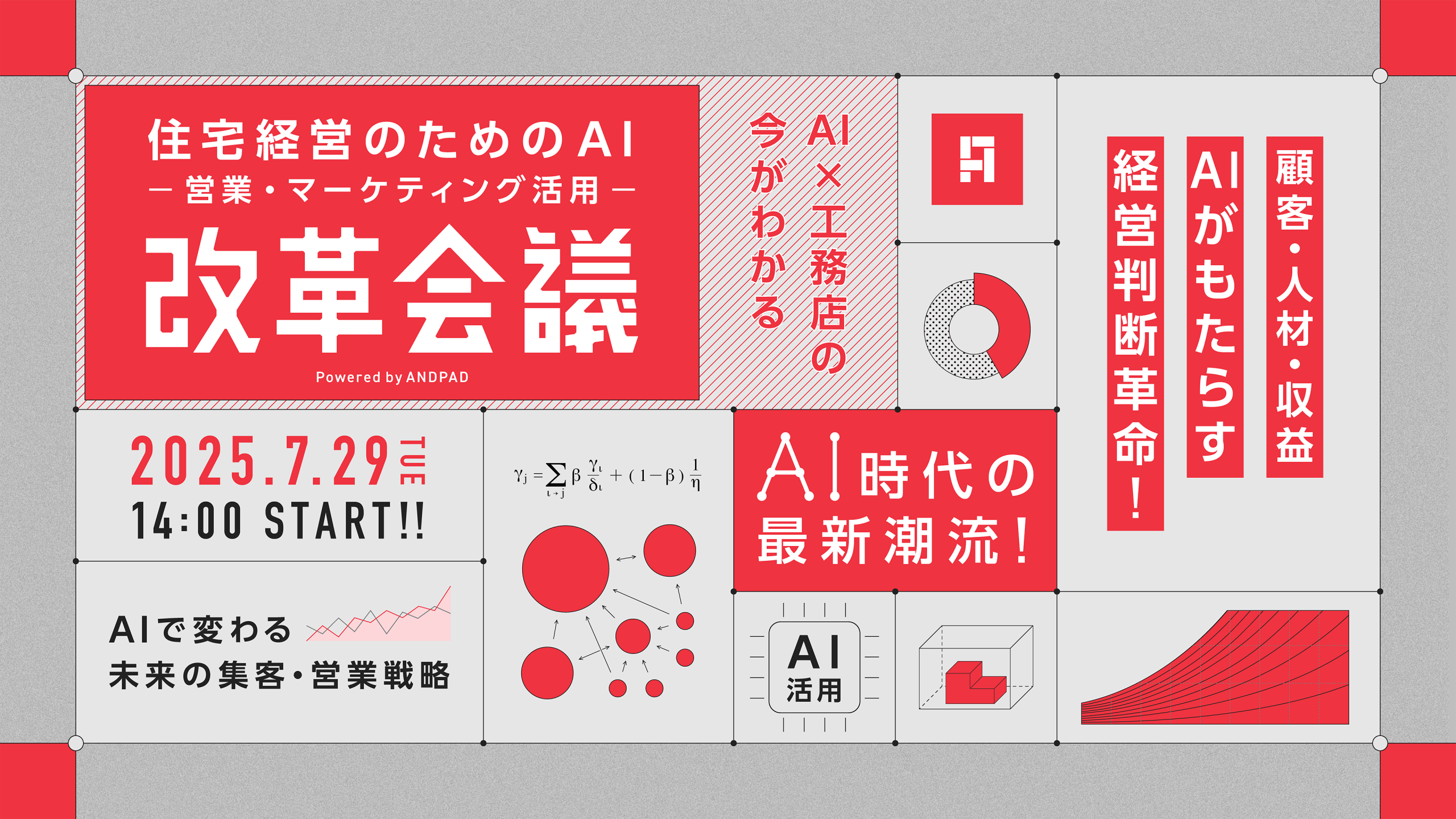文字サイズ
小
中
大

より良い家づくりへの挑戦 ~電気工事士が現場の情報共有を徹底する理由~
ANDPAD AWARD 2022「総合賞 〜西日本〜」3位/受賞ユーザーインタビュー
- ANDPAD・AWARD
- 専門工事
- ユーザー限定
こちらのページは
ANDPAD IDをお持ちのユーザー限定
のページになります。
ANDPAD IDをお持ちのユーザー限定
のページになります。
ANDPAD IDでのログインを
お願いいたします。
お願いいたします。