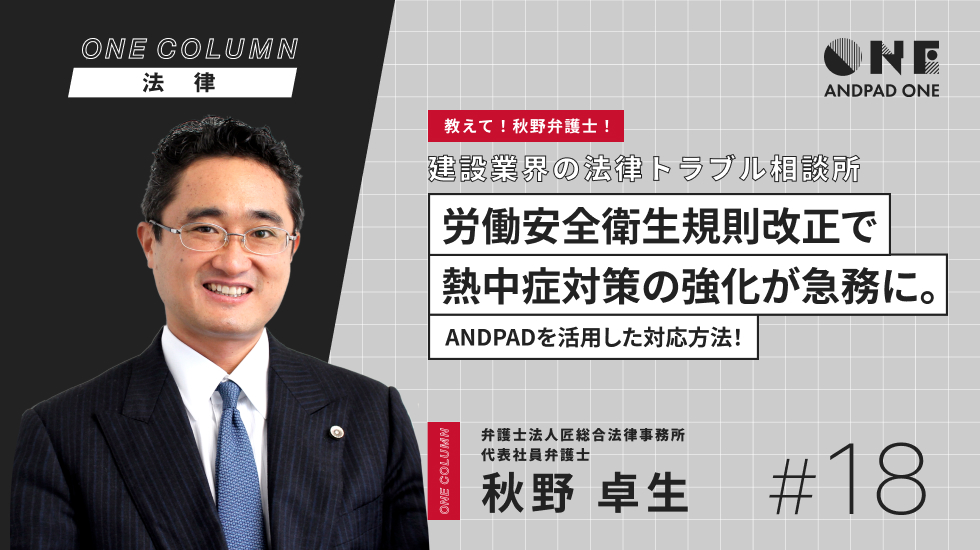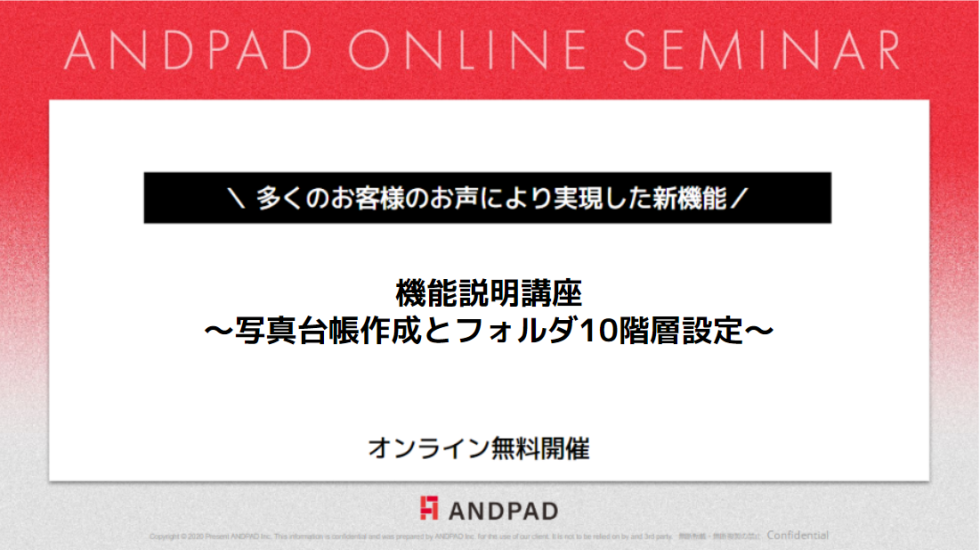目次
「自然と共に生きる暮らし」をコンセプトに、高気密・高断熱で長寿命な住まいづくりを追求しながら、地域の価値となる風景の創造にも取り組んでいる増木工務店。前編では、多数の受賞歴を誇る同社の家づくり・まちづくりと、同社で働く方々を紹介した。後編では、現在の事業ドメインを定めるまでの道のりや同社の経営戦略・人材戦略、今後のビジョンについて詳しく掘り下げていく。
地域工務店・コミュニティ有識者との出会いで事業方針が固まった
「土を残して、緑を植える」「価値ある建物を後世に繋ぐ」をコンセプトに掲げ、地域の風景となる緑のまちづくりに尽力する同社。増木工務店として分社化する以前は、同社は総合建設業を営む「増木工業」の木造部門だったが、当時と現在での家づくりに変化はあるのだろうか。
齋藤さん: 以前は、入札での公共工事を手がけている地場ゼネコンの一部門だったこともあって、私を含め、価格勝負で競り勝つのがセオリーだと考えているような風潮がありました。自分たちが建てた家の価値を見い出して発信したり、その価値を5年、10年と継続して提供しようという取り組みは少なかったです。長年の実績があったため銀行や地主の方々からは知られていましたが、一般のお客様からの認知度は低かったです。私は、木造部門を率いていたため、「このままのビジネスモデルでいいのだろうか」と感じていました。

株式会社増木工務店 代表取締役 齋藤 洋高さん
そんなとき、齋藤さんは、相羽建設株式会社(東京都東村山市)が主催する「木造ドミノ研究会」に出会う。木造ドミノ研究会は、スケルトン(構造)とインフィル(内装・設備)が分離した構造となっている「木造ドミノ住宅」の建設と普及に取り組んでいる団体だ。

木造ドミノ住宅は、家族のライフスタイルの変化に合わせて柔軟に間取りを変えられるシンプルな箱の家だ。「永く住み継ぐ家」を目指す同社の建物の基本構造となっている。(HPより転載)
ANDPAD ONE編集部より
齋藤さん: 2016年に木造ドミノ研究会に加盟し、相羽建設の相羽健太郎さん、木造ドミノ研究会 事務局長(前:相羽建設 相談役)の迎川利夫さんといった地域工務店の方々、コミュニティづくりの有識者であるチームネットの甲斐徹郎さんと出会ったのが、当社の事業ドメインを決める大きなターニングポイントになりました。
みなさんとの出会いがなかったら、広報戦略も家づくりの方向性も今と全く違っていたと思います。相羽社長をはじめ、みなさんに面倒を見ていただき、気にかけていただきました。足を向けて寝られない人たちが多すぎて、どこを向いて寝ればいいかわからないくらいです(笑)。

同じ志を持つ地域工務店・企業の支えを受け、増木工業の木造部門は、「土を残して緑を植える家づくり」へとコンセプトを定め、変革していった。認知度向上に向けて、SNSでの情報発信など、広報戦略の強化も図っていったが、他部門からは懐疑的な声もあったという。
齋藤さん: 社内からは「SNSでお客様が呼び込めるわけがない」「広報で飯が食えるか」といった厳しい声も上がりました。ただ、木造部門としては納得感を持ってお客様に向き合えるようになっていたので、自分たちが手がけている事業の価値を信じて、コンセプトに沿った家づくりと広報活動を粘り強く進めていきました。その結果、さまざまなコンテストで賞をいただいたり、メディアに取り上げていただいたりするようになっていったのです。

「農ある暮らし」を提案するまちづくりが転機に
同社の地道な取り組みが実を結び、注目を集めるきっかけとなったのが、「新農住コミュニティ野火止台」だ。このプロジェクトは、同社の顧客だった地主から寄せられた「先祖代々引き継がれた800坪の畑を購入してもらえないか」といった相談からはじまったという。
相続税の問題や後継者不足によって土地が手放され、宅地化のためにアスファルトやコンクリートで埋まり、良質な土や緑が失われていく……そんな状態に危機感を抱いていた同社は、地場の工務店として何ができるだろうかを考え抜いた。自問自答の末にたどり着いたのが、「新農住コミュニティ野火止台」だった。

HPより転載
「新農住コミュニティ野火止台」は、全18棟は建てられる敷地面積に、あえて15棟の分譲住宅を建て、その余白に住民共用の畑や果樹園、防災広場、縁道などを設けているのが特徴だ。また、住宅にはエネファームやパッシブエアコンといった高性能な設備を取り入れ、耐震性能や断熱性能を担保。構造は、間取りの可変性とメンテナンス性の高い木造ドミノ住宅を採用している。
齋藤さん: 当時は、経営状況にゆとりはなく、「新農住コミュニティ野火止台」は私たちにとって失敗の許されないプロジェクトでした。売り出しをはじめてみたらものすごい反響で、行政や同業他社の視察も多く、「抽選で販売できるかも」と思うこともありました。
ところが蓋を開けてみると、見学に来られた方は一様に「良いね」と言ってくださるものの、購入にはなかなか結びつきませんでした。10年、20年経っても色褪せないまちにしたいと、私たちの理想を詰め込んだのですが、これまでの分譲住宅地にない要素も多かったので、ビジネスとして成立させるのが難しくなってしまったのです。
このプロジェクトを通じて、用意された土地の上に思い思いの家を建てる注文住宅と、分譲住宅は似て非なるものだと痛感しました。一定期間内に引き渡しをして資金回収をする、不動産流通にうまく乗せていく戦略が必要なのだと、あらためて認識し直したプロジェクトになりました。
その後、「新農住コミュニティ野火止台」は無事に購入者が決まり、今は15世帯の方々が畑で作物を育てたり、農業アドバイザーを務めてくれている地主さんと交流したりして、暮らしを楽しんでくださっています。

「理想の家づくりと不動産ビジネスを両立させる重要性を学んだ」と話す齋藤さん。現在は、このプロジェクトで得た経験をもとに、自社物件の資産価値を高める取り組みを行っているという。
齋藤さん: 自社が建てた建物の資産価値を高める活動に力を入れているのも当社の特徴です。特に、直近5年間で入居していただいたお施主様の住宅は基本性能の高い建物なので、再販するときにその価値をしっかりと伝え、当時の購入金額や支払金額で売却ができるような取り組みを進めています。もし転勤や移住といった予期せぬライフイベントが起きても、購入時に近い金額で売却できれば住宅ローンの負債を抱えるリスクは減りますし、次の住み手がすぐに見つかるようであれば定期借家に出す方法も検討できます。
さらに、こうした資産価値を不動産会社にきちんと伝えるために、宅建士の資格を持つ髙木さんも新しい取り組みをはじめている。
髙木さん: 不動産や中古住宅の評価方法、流通の仕組みをあらためて学びたいと考えていた所、当社が加盟しているJBN(※Japan Builders Network。全国の地域工務店から成る組織)で岡庭建設の池田浩和さんにお声がけいただき、「工務店不動産ワーキンググループ」の立ち上げに参加しました。
また、独自の視点と価値観で物件を紹介している「東京R不動産」さんとも、自社物件の価値をどのように伝えていくか、一緒に考えさせていただいています。
大手不動産情報サイトの場合、どうしても駅からの距離や整形地といった検索軸で物件を探されるお客様が多いです。ですから、私たちのような高性能住宅を手がけている工務店は、流通に乗せる際に不動産会社さんに価値をきちんと届けることがより重要になってきます。こうした情報も、ワーキンググループを通じて工務店同士で共有ができればと思っています。

株式会社増木工務店 取締役 髙木 恭子さん
社員の積極的なチャレンジを支える評価制度と財務基盤
地場工務店やコミュニティづくりの有識者との出会いによって、自分たちが本当に手がけたい住まいの方向性をしっかりと固めた同社。試行錯誤を繰り返し、ときには苦い経験もしながら事業を軌道に乗せていっている。
ただ、本当に結果が出るかわからないプロジェクトに携わり、泥臭くチャレンジし続けるのには相応の勇気と根気がいるだろう。同社の社員のみなさんがモチベーションを高く持ち、新しいことに力を注ぎ続けていられるのはなぜなのだろうか。
齋藤さん: 当社は、15年ほど前から人事考課の仕組みづくりをはじめ、評価制度を整備してきました。現在、人事考課は3カ月に1回、社長面談は年2回行っています。透明度の高い評価制度をもとに、一人ひとりの頑張りをしっかりと見た上で成長を後押ししたり、待遇に反映したりしているので、社員も会社の想いに応えようとしてくれているのだと思います。
また、増木グループ全体として「社員の給与水準の引き上げにも取り組んでいる」と齋藤さんは話す。
齋藤さん: 分社化してからの3年間、グループ全体で年間昇給率6%以上(※2)を実現しています。採用競争が激しい管理職世代において、給与がネックになって優秀な人材が採用できない事態は少しずつ減らせるのではないかと考えています。直近の目標では、社員の平均年収650万円を掲げており、徐々に年収1,000万円プレイヤーも増えています。
また、社員持株会を設立し、利益を社員に還元する仕組みも整えています。今後は、新卒で入社した社員が定年する際の退職金として、現金で1,500万円、株で500万円=2,000万円の退職金支給を目指しています。

(※2)2024年の厚生労働省の調査によると日本の年間昇給率は大企業で4.8%、中小企業で3.7%。2025年の春闘でも平均4.1%となっており、同社の昇給率の高さがうかがえる。
さらに同社は、自社の財務諸表をHP上で公開しているという。上場企業と同様に、お客様や取引先、金融機関、社員といったステークホルダー全体に経営状態を明示することで、会社の信用力を高めたいとの考えだ。
「財務諸表をもとに描いた成長戦略を共有することで、自分も成長の原動力になろう、一緒に走っていこうと思ってもらえたら嬉しいですね」と齋藤さんは期待を込める。
社員の人生をまるごと受け入れる採用が会社の成長につながっていく
社員が心置きなく新しいことにチャレンジできるように、モチベーションを高める制度の構築に取り組む増木グループ。分社化の目的も、創業家の資産を残すためではなく、増木グループの「人」を守り、育てるために行われたものだという。
また、10年にわたって続けている米沢鶴城高校(旧:米沢工業高校)出身者の採用活動も同社の人材戦略に深く関わっている。
齋藤さん: 当社のビジネスモデルは、「人が増えれば利益が上がる」という仕組みではないので、純粋に建築を志している人材にきてほしいと考えています。
米沢鶴城高校の場合、長年採用活動を継続していることもあって、当社の想いに共感できそうな学生に、先生が紹介してくださっています。来年度入社予定の内定者も、私たちのHPを見て「自分のやりたいことが詰まっている」と話してくれたそうです。人材採用が難しい今の時代において、先生から紹介をいただけること、若手を継続的に採用できていることは、私たちの方向性が間違っていなかったことの証だと思います。

来年度も、米沢鶴城高校から1名の卒業生が同社に加わる予定になっている。齋藤さんは、その学生から「ある希望」を伝えられ、快諾したという。
齋藤さん: 来年入社予定の内定者は山形県飯豊町の出身なのですが、飯豊町では毎年7月〜9月にかけて町内各地区の神社で獅子舞が舞う「獅子まつり」が行われるそうです。内定者の住んでいる地域はほぼ全員が顔見知りで、それぞれが獅子まつりでの役割を担っているとのことで、「就職してからも獅子まつりに出られるでしょうか?」と質問してきました。
私は、「もちろんぜひ参加してきてほしい」と伝えました。地域の伝統芸能として受け継がれてきたものを守り続けていく姿勢は、私たちが手がけているまちづくりに通じるものがありますし、まつりへの参加はコミュニティ醸成の参考にもなると思います。就職してからも、地域への想いを大切にまちづくりに取り組んでほしいと考えています。

仕事に見合ったスキルや資格を持つ人材を確保する「ジョブ型雇用」が進むなかで、同社は建築への想いを重視し、個人の生きがいやプライベートの活動をも尊重すると宣言する。まさに、「社員の人生をまるごと受け入れる」新しい採用のあり方といえるだろう。
地域の発展を見つめ続けてきたまなざしを、今度は未来のまちづくりに向ける
最後に、同社のみなさんに今後の展望について伺った。
髙木さん: 総合建設会社として培ってきた歴史や信頼と、まだ立ち上がったばかりの工務店としてのベンチャースピリット。この相反するふたつを備えている企業はなかなかないと考えています。戸建住宅専門の工務店では対応が難しい分譲地の開発にも携われますし、自然環境への配慮といった時代のニーズにも対応できるのは、私たちならではの強みです。「土を残して、緑を植える」のコンセプトを軸にして、今後もスピード感を持って新しいチャレンジをしていきたいです。
また、東京R不動産さんをはじめ、建築に関わるさまざまな業種の企業との連携も深めていきたいです。現在、産業廃棄物の再資源化100%を目指している石坂産業株式会社(埼玉県入間郡三芳町)さん、大地の再生活動に取り組んでいる株式会社中央園芸(埼玉県大里郡寄居町)さんともつながりができています。人に会いに行って話をすることで、どんどん新しい取り組みができているのは本当に楽しいです。私たちは、家を建てることを得意としている工務店ですが、いろいろな面で協力し合える会社さんとつながり、一緒になってまちの風景や環境を変えていきたいですね。

山口さん: 私は、日々ニッチな層に向けて当社の魅力を届ける仕事をしていると感じているのですが、本来であれば自然環境を大切にするまちづくりについて、もっと多くの人が考えるべきだと思っています。
近年記録的な猛暑が続いています。多くの人が木陰を選んで歩いているのを目にするたびに、なぜ自分の家には木陰を作らないのだろうと不思議に思います。地域の工務店が建てた木陰のある家がどんどん広がっていけば、まち全体の風景は変わっていくはずです。今後も地域の工務店同士で協力して情報発信を続けていきたいと思います。

株式会社増木工務店 技術営業・広報 山口 愛莉沙さん
齋藤さん: 今のメンバーを「人に慕ってもらえる」「人を束ねられる」コアメンバーへと育てていきたいので、一気に人は増やさないつもりです。現在の規模感のまま売上向上を目指し、高い利益率をキープできる組織を作り上げ、まずは社員の給与を上げていきたいです。
また、私たちがしていただいたように、同じ業界で課題を抱えている工務店さんの助けになるような活動もしていきたいと考えています。そのためには、会社としての資本や財務基盤が強固でなければなりません。
また、私たちの目指すまちづくりができるチャンスを逃さない体制もつくっておかなければならないと感じています。例えば、億単位の土地を譲ってもらえるような話が巡ってきたときに、当社だけで資金を調達できる環境を整えておいたり、まわりの工務店や投資家に声かけをして資金を集められるような関係性をつくったりと、さまざまな未来を想定して企業体力をつけていきたいと思います。

齋藤さん: 「自分が信じた仕事をしていればいつか声をかけてもらえるんじゃないか」「声をかけてもらったときに勝負すればいいんじゃないか」と思っていた時期がありました。ただ、実績のない会社にはやはりチャンスは巡ってこないですし、仮にチャンスが巡ってきたとしても、その時点から準備をはじめるようでは期待に応えることはできないでしょう。
「新しいことをはじめる」と聞くと華やかな仕事に思えるかもしれませんが、実際はとても泥臭いものです。自分の引き出しから溢れるぐらいのアイデアや情報を常日頃から集めておく。やりたいことのために考察を深めておく……そういった地道な積み重ねが、いざ声がかかったときに素早く行動できる原動力になるのだと思っています。
また、自分たちにとってのブレない軸を持ち続けることも大事にしたいです。理想と現実のバランスを取っていく難しさはありますが、その都度自分たちの原点に立ち戻り、譲れないものを貫き通していきたいですね。

同社のコンセプトハウス「トコみど」にて。前列左より、髙木さん、山口さん、齋藤さん。後列左よりアンドパッド鯉沼、コミュニティマネージャーの平賀
総合建設会社として積み重ねてきた信頼と実績を大切に、地域に根ざした工務店として新たな歴史を刻みはじめた同社。長年受け継がれてきた緑の風景を守るために、ゆるぎないコンセプトを持ったまちづくりに挑戦し続けている。
地域と哲学をともにする地域工務店・関連企業と協力し、新しいことに取り組んでいる同社ではあるが、その根幹には創業家が150年にわたって大事にしてきた「人」への想いがある。人を育て、土を育て、緑を植える――いつでも原点に立ち返り、覚悟を持ってまちづくりに取り組む同社のチャレンジに、引き続き注目していきたい。

街づくり事業・新座市新堀分譲プロジェクト「ナリワイテラス のきの根」もスタート。城西大学と連携した、暮らしと小商いが融合する”新しい街づくり”のプロジェクトが始動している。https://www.masuki-koumuten.com/nariwaiterrace-nokinone
| URL | https://www.masuki-koumuten.com/ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役: 齋藤洋高 |
| 設立 | 2022年 |
| 本社 | 埼玉県新座市野火止三丁目10-5 |