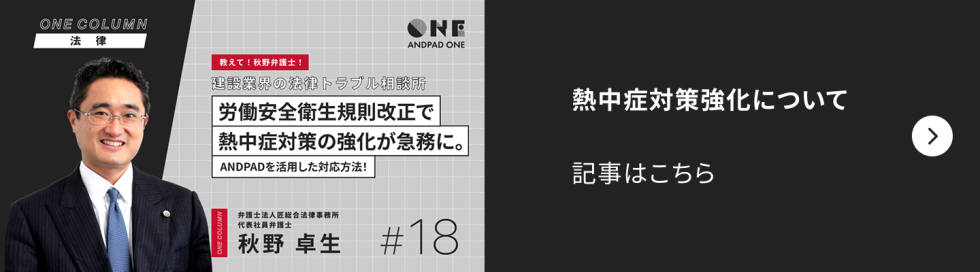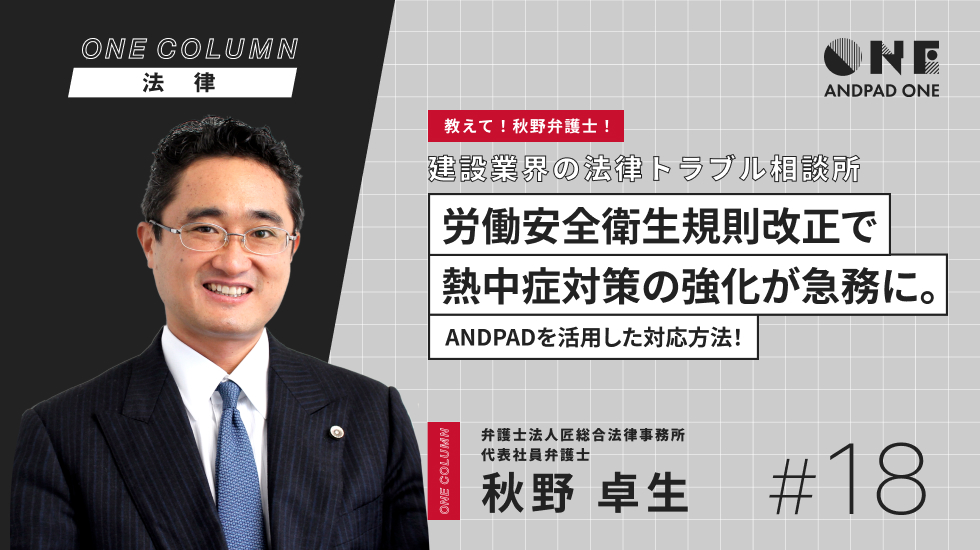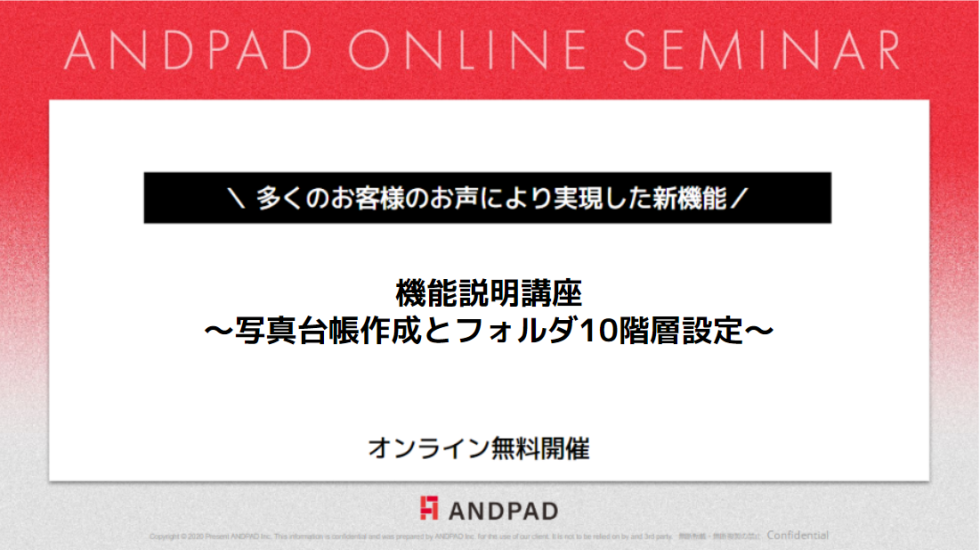目次
「土を残し、緑を植える」をコンセプトに掲げ、自然と共に生きる暮らしを提案している増木工務店。高気密・高断熱で長寿命な住まいづくりを追求しながら、緑豊かな風景の創造にも取り組んでいる地域密着の工務店だ。
同社は、明治5年に創業した1軒の材木屋「増田木材店」をルーツに持つ。増田木材店は、時代の変遷とともに柔軟に事業形態を変え、総合建設業・不動産業を手がける増木工業株式会社へと発展を遂げた。その増木工業のホールディングス化にあたって木造部門を分社化し、誕生したのが「増木工務店」だ。
同社は、創業150年の歴史を有する地場ゼネコンとしての信頼と実績を基盤に、生まれたばかりのベンチャーだからこそできることに果敢に挑戦している。それが、土と緑と共生するコミュニティの創造だ。同じ志を持つ地域工務店・企業と手を取り合いながら、今新しいまちづくりの歴史を刻み始めている。
今回は、分社化によって新しい一歩を踏み出した同社のみなさんにインタビューを実施。前編では、数々の受賞歴を誇る同社の住まいづくり・まちづくりの概要と、同社に集う「人」について紹介をしていく。後編では、長年にわたって地域の移り変わりを見てきた工務店の経営戦略や「人」への投資に焦点を当てながら、今後の展開について迫っていく。
創業150年の歴史と「人」を未来へつなぐためにホールディングス体制に移行
埼玉県新座市野火止に本社を置く増木工務店。本社から車で1時間圏内を施工エリアと定め、地域の職人と力を合わせ、土と緑を残す家づくりに取り組んでいる。増木工務店の設立は2022年。しかし、同社が所属する増木グループの誕生は約150年前にまでさかのぼる。明治5年、増木グループのルーツである増田屋は、薪や炭、材木の生産販売を営む商店として創業。戦後は、塩・タバコ・酒の販売も手がけ、地道に商いを続けてきた。1946年には木材の販売・建設業を手がける増田木材店を設立。その後、増田木材有限会社、増木工業株式会社へと名称を変え、建設業・不動産業を幅広く展開する企業へと発展を遂げてきた。
そして2022年、創業150周年の節目に、持ち株会社である増木ホールディングスを設立。増木工業が擁していた「総合建設業」「リフォーム・不動産事業」「木造住宅の建築事業」の3部門を分社化し、完全子会社とした。現在の増木工務店の前身は、増木工業の住宅事業部である。
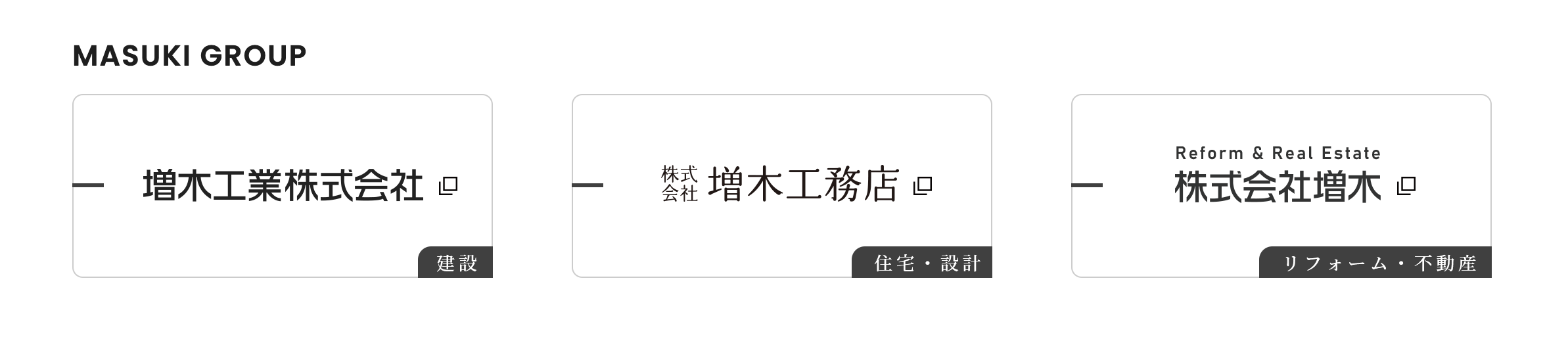
増木ホールディングスには現在、建設を担う「増木工業株式会社」、木造建築・設計を担う「株式会社増木工務店」、リフォーム・不動産を担う「株式会社増木」の3社がグループ企業として参画している。
齋藤さん: ホールディングス体制に移行し、各事業部が独立採算で運営する完全子会社となったことで、それぞれ独自性を活かした取り組みに特化できるようになっています。建設不況が叫ばれて久しいですが、分社化以降、増木グループは増収増益を続け、過去最高益も記録しています。
ただ、増木グループの創業家は、自分たちの資産を増やすために分社化したわけではありません。150周年を機に「同族承継をしない」と宣言していますし、金融機関や専門家から売却提案を受けても、「お金ではなく人を残すために分社化する」と提案をつっぱね、私たちが事業に集中しやすい環境を整えてくれました。なかなか真似のできないことだと感じています。

株式会社増木工務店 代表取締役 齋藤 洋高さん。増木工業株式会社に入社後、設計職として長年経験を積み、木造部門の責任者も歴任。2022年の分社化を受けて、増木工務店の代表に就任した。
「土を残して、緑を植える」――その想いが結実した家づくり
埼玉県新座市は、都心部のベッドタウンとして栄える一方、豊かな自然も残っているエリアだ。武蔵野の風情を残す雑木林、清らかな水が流れる野火止用水、四季折々の草花が楽しめる緑道は、地域住民の憩いの場となっている。
地域とともに歩んできた増木グループの一員だからこそ、同社は「土を残して、緑を植える」をコンセプトに掲げ、建物づくりに取り組んでいる。季節の移ろいや畑の実り、自然を味わう手仕事が楽しめる環境づくりを通じて、緑あふれるまちの風景を残すべく、住む人に寄り添った家を建てている。
また、「価値ある建物を後世に繋ぐ」ことも、同社の家づくりのコンセプトになっている。ライフスタイルが変わっても長く住み続けられる構造と快適性を重視し、高断熱・高気密でエネルギー使用量を抑えられる住まいを実現。また、環境への負荷を軽減するため、土に還る環境に優しい天然素材での家づくりも追求している。

今回取材を実施した同社のコンセプトハウス「トコみど」での一コマ(埼玉県所沢市)
同社は、この2つのコンセプトを軸に、住宅事業、まちづくり事業、木造施設建築事業、性能向上リノベーション事業を展開。コンテストでの受賞歴・メディア掲載も多く、年々注目度が高まっている。ここからは、同社の受賞歴を振り返りながら、事業内容を紹介していこう。
まず、性能向上リノベーション事業においては、「性能向上リノベデザインアワード2022」で優秀賞を受賞している。築43年の中古物件に耐震・断熱改修リノベーション工事を実施し、無断熱だった物件を断熱等級6・HEAT20 G2レベルに向上させ、耐震等級3相当の性能も実現した。長年大事に住まいを手入れしてきた売主の想いも引き継ぎ、新築住宅に見劣りしないデザインも叶えている。これが同社が初めて手がけた性能向上リノベーションというから驚きだ。

性能向上リノベデザインアワード2022・優秀賞受賞/築43年•想いと時間を紡ぐリノベーション(HPより転載)
また、「性能向上リノベデザインアワード」において、同社は2024年にも「選考委員賞」を受賞している。受賞した物件は、現在同社がコンセプトハウスとして運営している「トコみど」だ。今回の取材は、この「トコみど」で実施した。

住まい手が大事に守ってきた木々と畑を受け継いだ「トコみど」。土と緑のある暮らしの豊かさをお客様にダイレクトに提案できるように、同社の社員も畑仕事や季節の手仕事を「トコみど」で体験している。同社のショールームとしての役割も担っているが、いずれは地域の方々も利用できるオープンスペースとして活用していく考えだ。(HPより転載)
「トコみど」は、同社が10年前に建てた戸建住宅に断熱リノベーションを施し、10年前の最高等級・断熱等級3を、断熱等級7・HEAT20 G3へと向上した物件だ。太陽光発電とOMソーラーの両方を兼ね備えた「OMクワトロソーラー」を屋根に搭載し、エネルギーの自給自足も実現している。経年美化し、味わい深くなってきた自然素材の雰囲気はそのままに、耐震性・快適性を大きく向上した住まいとなっている。

「トコみど」は、耐震性に優れたパナソニックのテクノストラクチャー工法を採用。また、地震発生後の建物安全性を見える化するAI耐震診断装置「Aiシル」(設計:松本設計ホールディングス株式会社)が設置されている。「Aiシル」は、震度3以上の揺れがあった際に、センサーが即時に家の安全性を診断し、建物の損傷度合い、ダメージを受けた箇所、避難が必要かどうかを音声とLEDランプが点滅して知らせてくれる。「Aiシル」は遠隔でも状況を確認できるため、親族が状況を把握したり、工務店が重点的に補修すべき地域を把握したりするのにも役立つ。
次は、住宅事業における受賞歴を紹介していこう。同社は、注文住宅の建築に加え、分譲住宅の開発プロジェクトを「緑のまちづくり」事業として展開している。このまちづくり事業において、同社は2019年にグッドデザイン賞を受賞した。受賞したプロジェクトは、全15棟の戸建住宅で構成された分譲地「実りある暮らしの街~新農住コミュニティ野火止台~」だ。
「新農住コミュニティ野火止台」は、緑のある風景と「農ある暮らし」が楽しめる、これまでにない分譲住宅地だ。現在は、このコンセプトに共感した住まい手が集まり、新たなコミュニティが形成されている。齋藤さんは、「今後もまちづくりのプロジェクトには継続して力を入れていきたい」と話す。

「新農住コミュニティ野火止台」は、「グッドデザイン賞2019」に加え、「第7回 埼玉県環境住宅賞 協議会会長特別賞受賞」「住まいの環境デザインアワード2020 審査員特別賞・東京ガス賞」、「令和5年度 彩の国埼玉環境大賞 優秀賞」も受賞している。(HPより転載)
齋藤さん: 緑のまちづくりにつながる分譲開発プロジェクトは、今後もコンスタントに手がけていきたいと考えています。規模はそのときどきによって変わると思いますが、年間10棟は建てていきたいですね。
私たちが掲げている「土を残し、緑を植える」のコンセプトに共感してくださる地主さんから、「先祖代々受け継いできた畑を任せたい」「庭木や花を残す方法はないか」といったご相談を受けることが増えています。単なる土地の売買ではなく、豊かな土と緑をどうやって次世代に残していくか、未来を考える取り組みを一緒にしていきたいと考えています。

自然環境を大切にしたまちづくりに対して並々ならぬ想いを持つ同社は、いま新たなプロジェクトに取り組んでいる。それがコミュニティ型賃貸住宅「ケヤキファミリア」の開発プロジェクトだ。
「ケヤキファミリア」は、屋敷林や草花に囲まれた旧家の庭に4棟の小さな賃貸住宅を点在させたビレッジだ。「自然に還るように、暮らす」をコンセプトに、菜園・小さな小屋・庭を共有するコモンスペースを設け、外の自然に開かれた暮らしを提案する。このプロジェクトは、コミュニティ創出のプロジェクトを多数手がけている株式会社チームネット(東京都世田谷区)がプロデュースし、増木工務店が設計・施工を手がける。2026年初夏に竣工予定で、どんな暮らしが繰り広げられるか、今から楽しみな場所だ。
一緒に家づくりに取り組む、大工の労働環境改善にも尽力
天然素材を使った高性能な住宅、豊かな自然を活かした景観――こうした理想を実現するためには、自社の想いに共感してくれる地域の大工の力が欠かせない。そこで同社は、大工の労働環境改善にも力を注いでいる。
まず、大工の高齢化を受け、5年ほど前から木造大型パネルを用いた施工を導入。重量のある建材を扱う肉体的な負担を減らし、業務効率化によって工期短縮も実現している。
また、同じく5年ほど前から、上棟後の現場に仮設エアコンを導入する取り組みも実施している。2025年6月1日より「職場の熱中症対策」が義務化されたが、同社は業界に先駆けて熱中症対策に取り組んできた。
仮設エアコンの設置によって作業空間の熱さ指数(WBGT)を下げられれば、大工の負担が軽減されるだけではなく、作業中の休憩の頻度を減らし、一日の作業量を増やすことができる。結果として、引き渡しまでの工期の精度を高めることができているという。
ANDPAD ONE編集部より
こちらの記事では、労働安全衛生規則改正におけるANDPADを活用した対応方法をご紹介しています。
さらに、同社は協力会社の後継者問題にも真摯に向き合っている。
齋藤さん: 「親方が引退したら組織運営が難しくなりそうだ」との声が上がっている協力会社はいくつかあります。万が一そうなったときには「当社で大工さんたちを引き受けるから、ぜひ声をかけてほしい」と伝えています。

営業、設計、施工管理、広報――職種の垣根を超えて活躍する社員たち
前身である増木工業の木造部門だった時代から、時代に先駆けた取り組みを続けてきた同社。分社化から3年、現在は新卒入社の若手社員やパートスタッフを含めて13名が勤務しているが、営業や施工、広報などと明確な役割分担はせずに、全員が幅広い業務に対応できるように人材育成を進めているという。

株式会社増木工務店 取締役 髙木 恭子さん
入社から7〜8年は現場監督として木造住宅や施設を担当してきました。今は技術営業として提案から設計、施工管理までトータルに任せていただいています。

株式会社増木工務店 技術営業・広報 山口 愛莉沙さん
齋藤さん: OMソーラーをはじめて導入したときや、スケルトン・インフィル方式ではじめて施工をしたときなど、当社で新しいものを採用するときには山口に現場に入ってもらっています。新しいことが得意で仕事が丁寧な大工さんがいるので、いつも山口とペアになって設計や段取りの取り合いを見てもらっています。当社の家づくりや現場をよく理解しているので、山口は広報も兼任しています。
山形県米沢市にも拠点を置き、採用活動や新しい取り組みを展開
同社は、山口さんの出身校である米沢鶴城高校の卒業生の採用活動を10年以上前から続けており、現在増木グループ全体で4名の卒業生が活躍中だ。卒業生との縁がある米沢市には、増木グループのサテライトオフィスとして米沢営業所も開設している。「埼玉一点集中での経営リスクを軽減したい」という増木ホールディングスの社長の考えを受け、BCP対策の一環としてコロナ禍以前の2019年に実施された取り組みだ。
また、増木グループの社長は「デュアルワーク/デュアルライフ」も提唱している。こうした同社の風土と自然環境を大切にする家づくりに感銘を受けた山口さんは、自身の故郷である米沢市に「もうひとつ暮らしの拠点がほしい」と考えるように。そして2023年、山形県でLCCM住宅(※1)を建てている。
(※1)LCCM住宅とは…LCCM(エルシーシーエム)は、ライフ・サイクル・カーボン・マイナスの略称。建設時、運用時、廃棄時において出来るだけ省CO₂に取り組み、さらに太陽光発電などを利用した再生可能エネルギーの創出により、住宅建設時のCO₂排出量も含めライフサイクルを通じてのCO₂の収支をマイナスにする住宅のことを「LCCM住宅」と呼ぶ。(参照:「ZEH・LCCM住宅の推進に向けた取組」国土交通省(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000153.html ))

HPより転載
山口さんの自邸は、同社初のLCCM認定住宅だ。住宅の施工は現地の工務店に任せ、同社は企画・設計・監理を担当した。今回のLCCM認定取得と地域工務店との連携で培ったノウハウを活かし、「今後は米沢起点のビジネス、エリア外での展開も検討していきたい」と齋藤さんは意気込んでいる。

創業150周年を迎えた地場ゼネコンのホールディングス化によって、独立した工務店へと事業転換した同社。ゼネコン時代からの地道な取り組みが徐々に花開き、同社が掲げる「土と緑を大切にしたまちづくり」は、地域の地主をはじめ、多方面から評価されはじめている。後編では、同社が現在の事業ドメインを定めるまでの道のりに迫りつつ、新しいチャレンジの土台となっている経営戦略・人材戦略を深掘りしていく。

| URL | https://www.masuki-koumuten.com/ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役: 齋藤洋高 |
| 設立 | 2022年 |
| 本社 | 埼玉県新座市野火止三丁目10-5 |