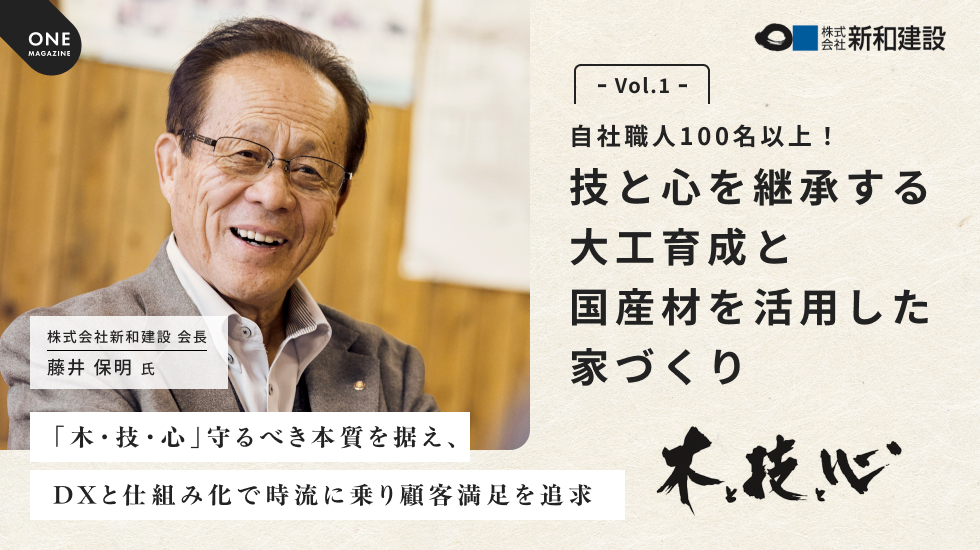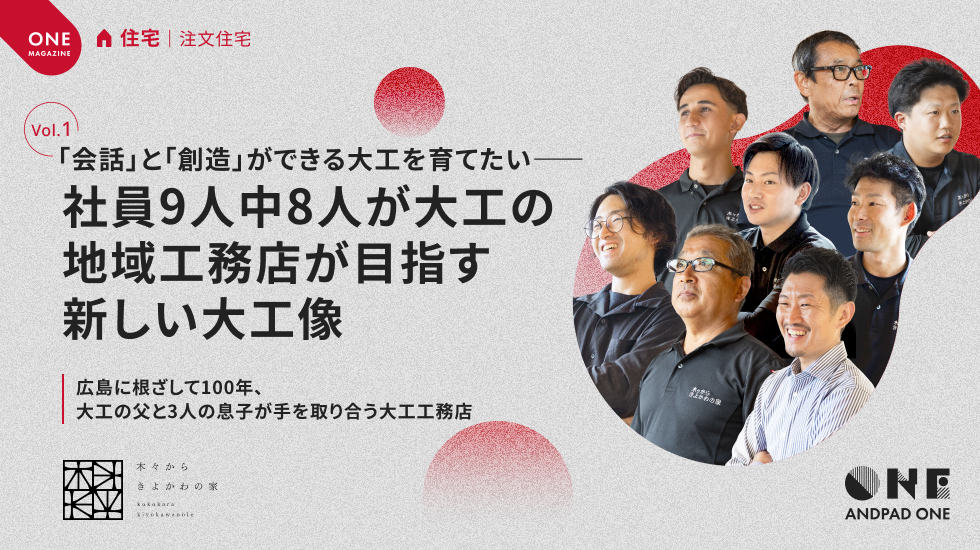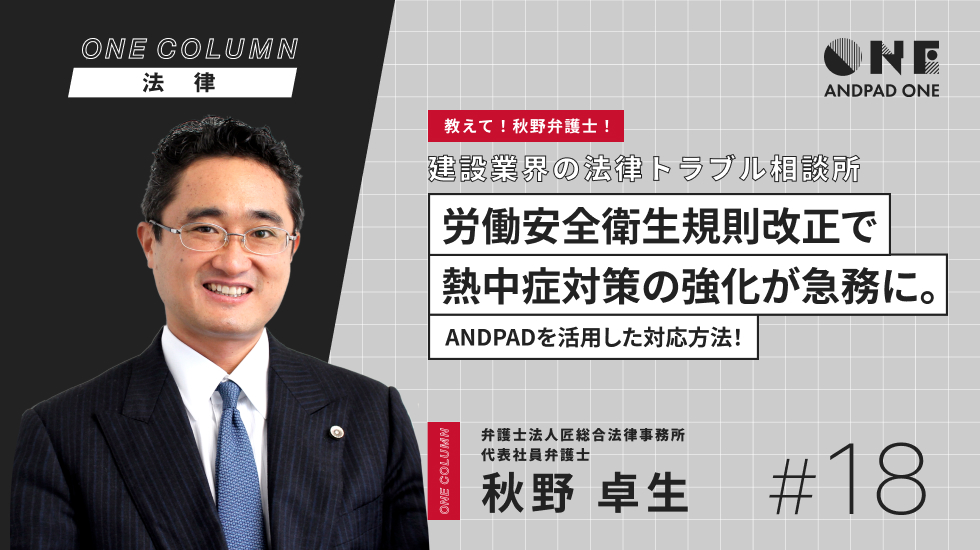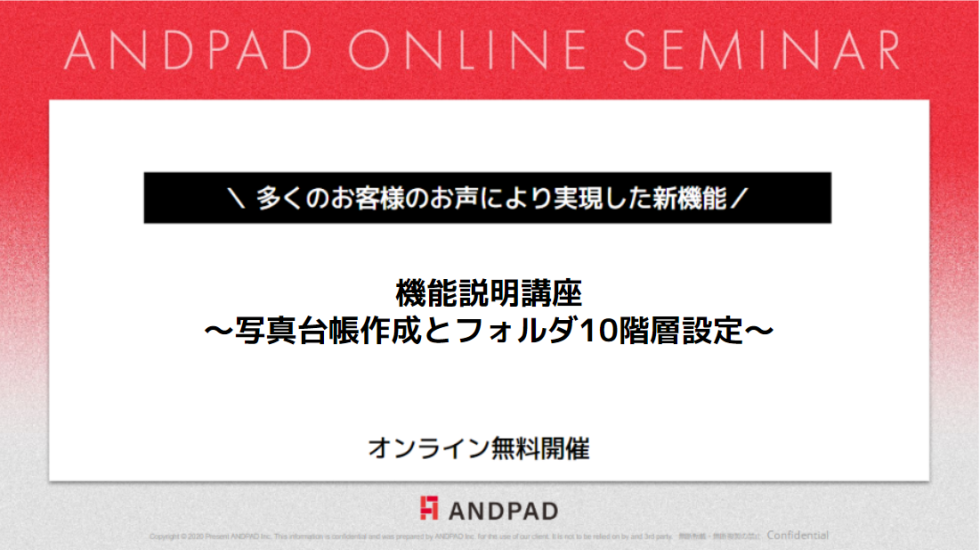目次
明治20年の創業以来、岡山県倉敷市に根ざして138年の歴史を刻んできた株式会社なんば建築工房。「人の住む家は、人の手で創る」をコンセプトに掲げ、職人の手仕事・心意気にこだわった家づくりに取り組む地域工務店だ。さらに、同社は「古民家再生」も得意としており、長年培ってきた専門技術を活かして、現在は古き良き町並みの保存活動や町おこしにも積極的に参加している。
そんな同社が手がける家づくりは、フルオーダーの注文住宅建築、古民家再生、古材を活かしたリフォームが中心だ。こうしたこだわりの家づくりを実現するのは、自社の職人たち。大工はもちろんのこと、左官職人や土木職人までもが在籍し、切磋琢磨しながら腕を磨く同社は、県内でも強固な存在感を放っている。
一方で、職人がこだわる家だからこそ、着工から完工までの工期が長期化したり、その結果利益率が低下してしまうことが長年の課題だった。こうした状況を受け、同社はANDPAD施工管理、ANDPAD受発注、ANDPAD引合粗利管理、さらには「Digima」(※)も活用し、全社の業務フローを再構築しながらDXを推進。その結果、粗利率は4.55%改善し、工期遵守の意識を醸成するなど高い成果をあげ、ANDPAD AWARD 2025「DXカンパニー部門」の「住宅 × SMB」カテゴリでは入賞を果たした。
同社のDXの取り組みはこちら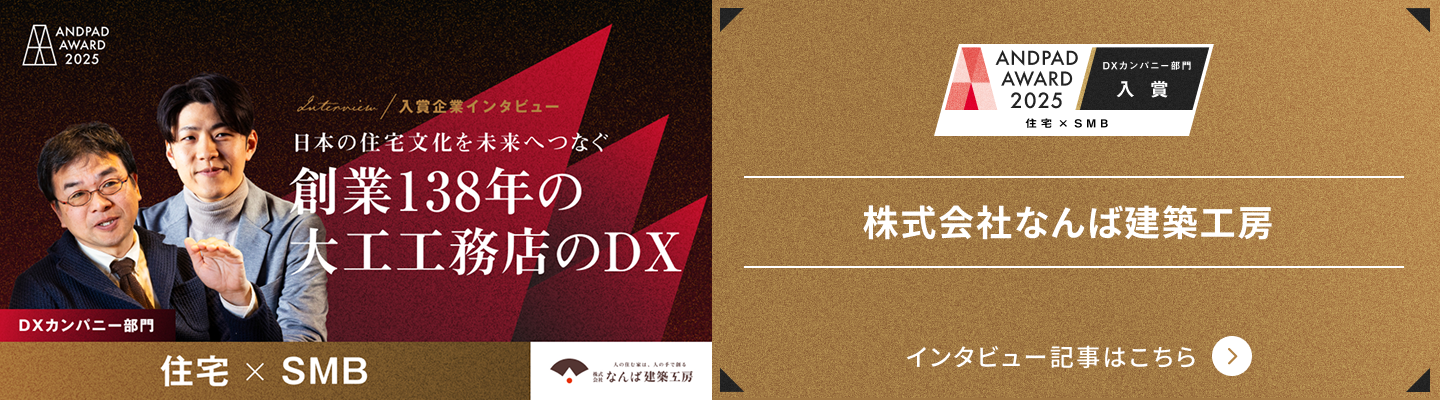
DXを推進することでコストや業務の無駄を省き、日本の住文化を未来へ受け継ぐ活動を行う同社。しかし、こうした現在の姿に至るまでの道のりは決して楽なものではなかった。
現在5代目の代表取締役社長を務める正田さんは、同社の傾いた経営を立て直し、自身の仕事だけに意識が向きがちだった職人の意識改革のもと、職人の手仕事や自社に眠っていた古材の活用に光明を見出す。それらを活かす事業ドメインとして、古民家再生を軸に据えた町おこしを定め、その活動は地域までもを変えていく大きなうねりとなっていった。
こうした強固なコーポレートアイデンティティを築き上げていくまでの軌跡に迫るべく、今回は正田さんにインタビューを実施。会社を再生させながら、社内外をいかにして巻き込みながら自社の強みを見出していったのか、そのストーリーは地域工務店の経営戦略において大いに参考になるだろう。前編では、正田さんの生い立ちと、同社へ入社するまでの前職での歩みについて迫っていく。
職人の手仕事、古民家再生を軸にした町おこしに強みを持つ大工工務店
なんば建築工房の創業は明治20年。岡山県倉敷市に拠点を構え、5代にわたって建築業を営む地域工務店だ。手がけるのは、新築注文住宅からリノベーション・リフォーム、古民家再生、商業建築、寺社の新築・補修まで実に幅広い。地域の暮らしを豊かにする家づくりをはじめ、地域の「家守り」としても信頼を得ている。
そのこだわりの家づくりを実現するのは、社員40人中半数以上の21人を占める職人たち。「職人の手仕事を活かした家づくりを通し、人を育て、技術を継承し、価値ある仕事をする」という経営方針のもと、自社職人の採用・育成に注力する同社。現在では、大工16名、左官職人2名、土木職人3名が切磋琢磨し合いながら腕を磨いている。

さらに、地域の宝ともいえる「古民家」の再生に注力していることも同社の特徴だ。古民家を新しい価値のある建物へと生まれ変わらせるだけではなく、やむを得ず解体となってしまった古民家からは古材を買い取り、リユースへとつなげている。自社倉庫に豊富にストックしている梁や柱、框、建具、道具は、マンションの一部屋に古民家風の空間をつくる「一部屋リフォーム」やリノベーション、新築注文住宅に用いることで、古材に新たな命を吹き込んでいる。

古材・古道具が豊富に揃う同社の倉庫。
そんな職人の熟練の技と古民家再生事業を軸に、同社では岡山県倉敷市下津井の町おこしに取り組んでいる。行政と協業しながら、空き家対策や古民家の利活用・再生、移住支援・住宅斡旋に励む同社は、自社の強みを地域にまで還元している。

空き家の活用に関して、児島商工会議所でセミナーを実施する正田さん(写真左)。下津井の宿「風待汐待(かぜまちしおまち)」(写真右)は、同社が築70年を超える古民家をリノベーションして開業した貸切の宿。空き家活用と町並み保存を両立している。詳細:風待汐待HP https://kazeshio.com/ja/
「いつか自分の力で大きな広い家を建てる」 自立を誓った幼少時代
そんな同社で5代目社長を務めているのが、正田さんだ。32歳で入社し、会社の経営危機のなか40歳で会社を引き継いだ。自社の強みを見出しながら、現在に至るまでいくつもの苦境を乗り越え、会社の在り方を根本から見つめ直し、変化を恐れず果敢にチャレンジを重ねてきた正田さん。そんな彼の原動力の起源には、幼少期の忘れられない体験があるという。
正田さん: 私は大阪で生まれ、奈良で育ちました。当時暮らしていた家は狭く、母に「早く広い家を買って」とせがんでいましたね。小学3年生のとき、友達の立派な家とおもてなしに感動し、自分もいつかこんな家に住みたいと母に訴えたことがありました。しかし、母からは「大きな家に住みたいんやったら、あんたが働いて、自分で建てられるように頑張りや!」と諭されました。その言葉を聞いて、私は心に誓いました。親に頼るのではなく、いつか自分の力で大きな家を建てられるくらい自立して、自分の力で生きていこうと。

このエピソードこそ、その後の数々のチャレンジの原点だったのかもしれないと振り返る正田さん。その後も、時折母の言葉を思い返しては自身を奮い立たせ、少しでも自分で使える小遣いを稼ぐためにアルバイトに励んだ。さらに、自立して生きるには、少し遠回りでも大学を出た方がいいと考え、両親を説得して猛勉強の末、岡山県内の大学へ進学。卒業後は新卒で岡山県内のパワービルダーへ営業職として就職し、住宅業界でのキャリアのスタートを切ったのだった。
過酷なパワービルダーで培ったハングリー精神と「顧客に誠実な家づくり」の軸
入社後の正田さんを待ち受けていたのは、想像を絶する過酷な日々だった。
正田さん: 時代はバブル崩壊後。会社は潰れかけで 、同期入社は15人いましたが、離職が後を絶たず1年後には5人にまで減ってしまうような状況でした。それでも、私が会社に残ったのは、強烈な上司の存在が大きかったですね。
正田さんは上司から、高圧的な言動などの心理的嫌がらせや、殴る・蹴るなどの身体的暴力まで受けたという。それでも、上司は当時の売上の筆頭株だったこともあり、会社は辞めさせることはなく、正田さんは覚悟を決め食らいついた。
正田さん: 「絶対に上司を追い越す」と心に誓い、とにかく仕事に打ち込みました。過酷な飛び込み営業にも屈せずがむしゃらに働いた結果、入社から3~4年目には、上司の成績を追い越し、会社で一番の売上を上げることができたのです。その後、上司は傷害事件を起こして退職。その後も私は会社に残ることを選びました。追い抜く目標としていた上司が退職したからといって自分も辞めてしまうのは、なんだか負けたような気がしたからです。
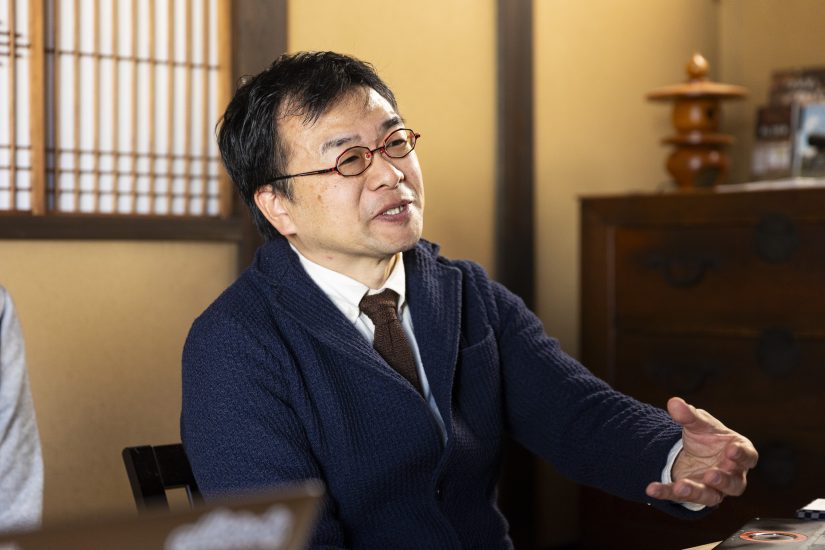
トップの売上成績を上げた一方で、会社の経営状態は依然として危機に瀕していたという。
正田さん: 専務が全社員を前にした朝礼で、「今月契約が取れなかったら潰れます」と告げるほどでした。そんな状況にあっても、私は「たとえ潰れるのであっても、やれることはやろう」と考えました。お客様に「もし会社が潰れたら、違約金は私が払います」と正直に伝えて、50万円の契約金をもらい、契約を成立させました。
かねてより、同社の大量生産・大量消費・利益重視の営業スタイルに疑問を抱いていたという正田さん。その違和感を出発点に、自身が大切にしたい家づくりの軸を見出していく。
正田さん: 住宅は多くのお客様にとって、生涯で最も大きな買い物です。それなのに、当時歩合制だったこともあり、強引な営業をする先輩社員や、お客様の意向を汲まずに契約を取り付けようとする同僚たちを見て、いたたまれない気持ちになりました。仕事を続けることが不安になり、母に愚痴をこぼすと厳しい言葉が返ってきたんです。
「あんたは会社が良くなるような努力をしたんか? 建築資格もないあんたが、お客様に喜んでもらうために何をしてきたんか言うてみ!」と。
何も答えられなかった自分を情けなく思いました。そこで、まずは目の前のお客様の声にしっかりと耳を傾け、お客様にご満足していただける提案をし、会社の業績を上げようと心に決めました。

その頃、後に正田さんの妻となる新入社員が入社。彼女は独自性と商品力に欠ける会社の方針に意見を発した。同じ課題意識を抱えていた正田さんと意気投合し、二人で「定額制で正直な木の家」というコンセプトに基づく事業を企画し社長に提案。これまで施工費用やローンに関して、顧客への説明が不十分だった状態を見直し、顧客に費用面での不安を抱かせない方針へと転換。社長からの承認を受け、1995年には定価制のブランドを立ち上げた。
正田さん: 今まで見学会をしても4組や5組程度の来場でしたが、定価制のこだわった「見学会のお知らせ」を作成し、新聞の折込チラシで宣伝しました。すると、普段は2〜3組しか来なかった見学会に、70組ものお客様が来場されたんです。涙が出るほど嬉しかったことを今でも鮮明に覚えていますね。
これまで私は、お客様が一生住む家があまりに商売の道具として扱われてきたことに心を痛めてきました。自社の利益を優先させるのではなく、お客様に寄り添った家づくりをしたい。このとき、私のなかで「お客様との家づくり」という、大切にしたい軸が芽生えました。

そして、結婚が決まった頃、妻に誘われて訪れた場所こそが、なんば建築工房の展示場だった。そこで正田さんは、本物の木が織りなす繊細で美しい佇まいの家を目にし、心底感銘を受けたという。
正田さん: 実は、妻がなんば建築工房の先代の次女だと知ったのは、結婚を決めてから挨拶に行ったときでした。その後、お世話になった前職への恩返しの気持ちで5年間ほど働きましたが、なんば建築工房が手がける家に出会ったときの感動が忘れられず。私たちが立ち上げた企画がヒットして、会社の業績が上がったタイミングで退職を決意しました。さらに、在職中に二級建築士と宅地建物取引士の資格を取得したことで、お客様のご要望を図面に起こせるようになり、対応できる業務の幅も広がりました。退職時に、会社に恩返しもでき盛大にお祝いして送り出してもらったことは、今でも私の原動力になっています。
こうして前職を退職し、なんば建築工房の門を叩いた正田さん。同社の木を生かした家づくりに惚れ込み飛び込んだものの、その先で正田さんを待ち受けていたのは、またしても苦難の連続だった。後編では、なんば建築工房に入社後、社長に就任し、現在の強固なコーポレートアイデンティティを築き上げていくまでの歩みに迫る。
| URL | https://www.nanbakenchiku.co.jp/ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 正田 順也 |
| 創業 | 1887年 |
| 本社 | 岡山県倉敷市児島上の町1-14-56 |