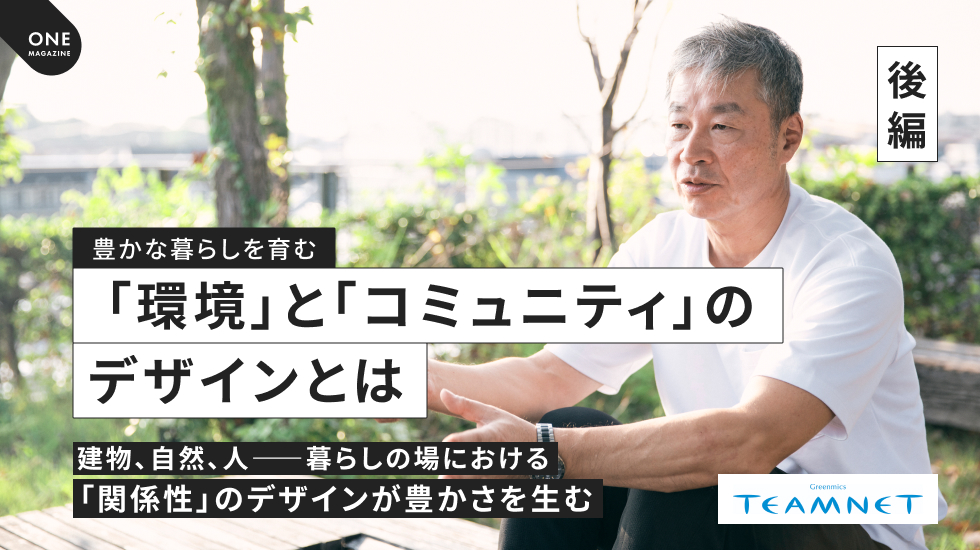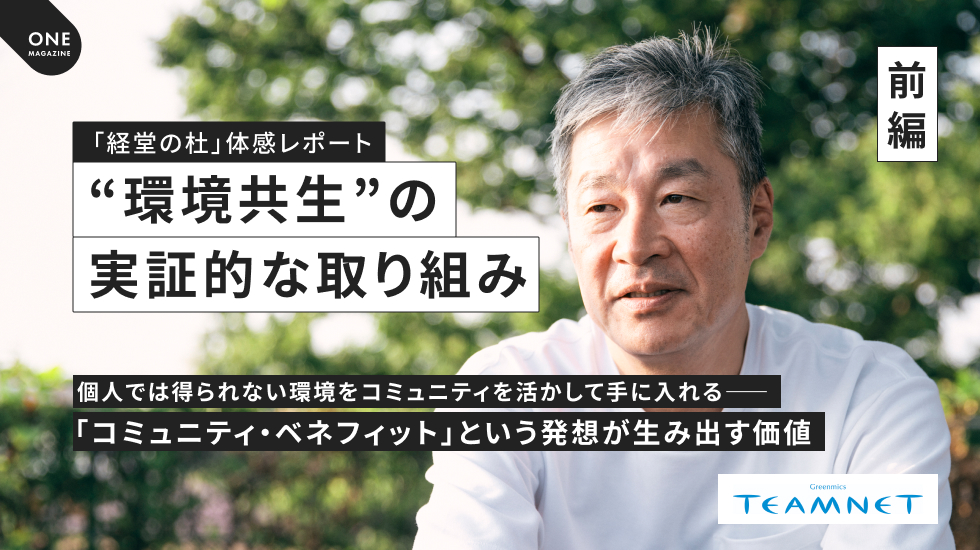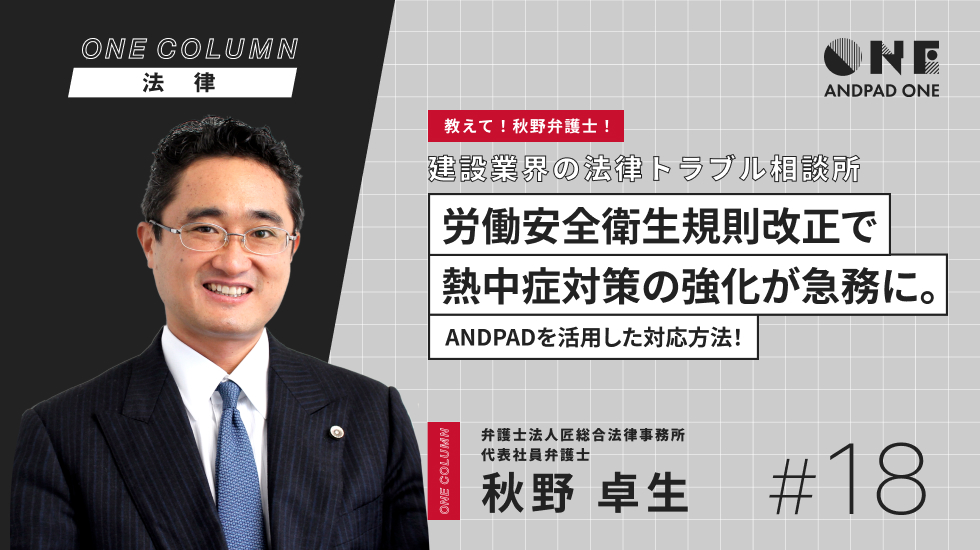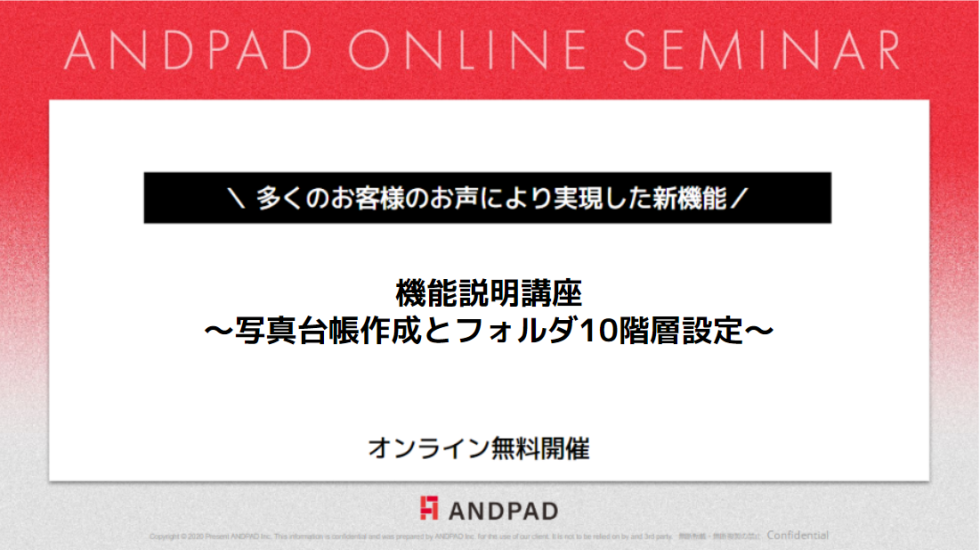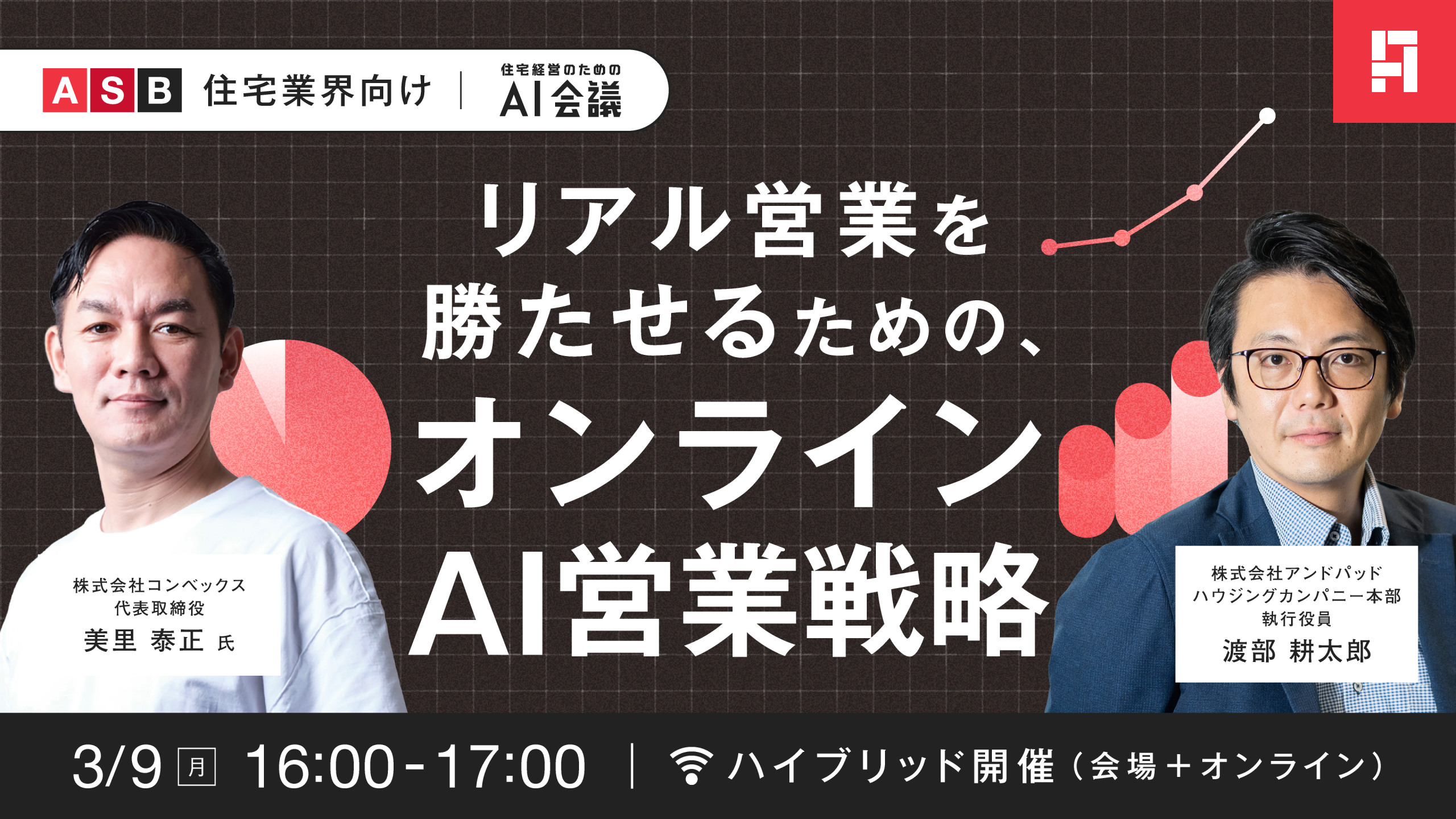目次
人口減少や少子高齢化によって、地域経済やコミュニティの衰退、空き家の増加、土地相続の問題は年々深刻化している。こうした現状を受け、国土交通省は2024年6月に「スモールコンセッション推進方策」を策定した。
スモールコンセッションは、現在使われていない公共施設や地域住民から寄付された古民家など、地方自治体が所有する遊休不動産の利活用に向けて、民間事業者と連携した事業を行い、地域課題の解決につなげていく取り組みだ。遊休不動産の再生の連鎖によって、エリア全体の価値を向上する「エリアリノベーション」の効果も期待されている。スモールコンセッションの取り組みは、地域に根ざした工務店やビルダーが地域貢献に関わっていく良い機会になると言えるだろう。
そこで、注目したいのが、株式会社チームネットがプロデュースしたコミュニティ型賃貸住宅「ケヤキファミリア」だ。「ケヤキファミリア」は、地主の抱えていた土地相続の課題を解決し、地域外から新たな住民を呼び寄せ、エリア価値向上に貢献する好事例と言える。この取り組みは、不動産の利活用と持続的な不動産価値の向上を図るコンセプトづくりという文脈において、スモールコンセッションを考える際の参考になるのではないだろうか。
前編では、甲斐さんが最初に手がけたプロジェクトであり、甲斐さんの自邸でもある「経堂の杜」ついて詳しくレポートした。後編では、コミュニティを「手段」にして事業に活かす「コミュニティ・ベネフィット」の考え方から、これからの不動産活用に役立つヒントを探っていく。
環境共生型住宅を広めるために独立 自邸である「経堂の杜」をモデルプロジェクトに
1995年の設立以来、「環境共生型住宅」を世の中に広めている株式会社チームネット。自然環境に寄り添った建物を建て、居住者がその環境を守る担い手となるようなプロジェクトを数多く手がけている。前編で紹介した「経堂の杜」をはじめ、集合住宅、社宅、まちづくり支援など、手がける内容は幅広い。
では、甲斐さんはなぜ「環境共生」をテーマに住まいづくり・まちづくりに取り組むようになったのだろうか。
甲斐さん: 私は大学卒業後、10年間マーケティング会社に勤めていて、ガラスや断熱材などを扱う建材メーカーを長く担当していました。私が勤めていた1990年代は、ちょうど日本で省エネブームが盛り上がっていたころで、省エネ基準の見直しや高性能住宅の普及が進みはじめていました。私も建材メーカー担当のコンサルタントとして、住宅の気密性・断熱性などについて深く学びながら、性能の高い建材をハウスメーカーや工務店にいかに普及させていくか、クライアントとともに事業戦略を練っていました。

株式会社チームネット 代表取締役会長 甲斐徹郎さん
甲斐さん: あるとき、マーケティング推進の一環として、高性能住宅の先進国であるスウェーデンやドイツを視察するツアーを企画し、建材メーカーのお客様に帯同する機会がありました。当初は、ヨーロッパで用いられている建材や設備など、ハード面を見て回ろうと思っていたのですが、当時すでにヨーロッパではハード面の技術開発はほぼ終わっていて、建築に関わる人たちの関心事は「環境」と「コミュニティ」へと移っていました。
特に印象的だったのは、スウェーデンで視察したビレッジです。そこは、30世帯ほどの戸建住宅が幼稚園をぐるっと囲むように配置されており、幼稚園に通う子どもたちを見守ることが暮らしの一部に溶け込んでいました。そして夜になると、幼稚園はバーへと一変。ビレッジに住む大人たちが集まり、優雅な時間を楽しんでいました。
このビレッジで時間を過ごし、「暮らしの豊かさは家の内部だけにあるのではない。外部の環境とその環境を共有し合うコミュニティが暮らしの豊かさに大きな影響を与えるのだ」と気づいたのです。これまで「高性能住宅さえ建てれば暮らしが良くなる」と考えていた、自分の世界観の小ささにはっきりと気づき、価値観が転換した瞬間でした。

アンドパッドのコミュニティマネージャー 平賀(写真右)がお話を伺った
甲斐さん: 日本に戻ったのと同じタイミングで、国が環境共生住宅推進協議会(現:環境共生まちづくり協会)を立ち上げ、環境と共生するまちづくりに乗り出したことを知りました。「環境共生」と聞いたとき、これこそ私が実現したい世界観だと感じ、日本に普及させたいと心から思いました。そのためにマーケティング会社を辞めて立ち上げたのが、チームネットです。
「環境共生」の持つ価値を世の中に示すために、まず私は自分の家づくりをモデルにしようと考えました。当時から世田谷に住んでいたので、世田谷で環境共生住宅を建てようと考えましたが、世田谷は地価が非常に高く、狭小住宅しか建てられません。郊外に行くことも考えましたが、都市の利便性と豊かな自然環境を二者択一で選ばなければならないのは残念だと考え、何とか両立できる方法がないか模索しました。
そこで思い至ったのが、コーポラティブハウスという手法の活用です。「世田谷に森をつくって暮らそう」と呼びかけて希望者を集め、個人単位では得ることが難しい豊かな自然環境をコミュニティ全体で得ようと考えたのです。コミュニティを「目的」とするのではなく、個々の住民が自分の豊かな生活を実現するために、コミュニティを「手段」として利用する。「コミュニティ・ベネフィット」のコンセプトは、ここで生まれました。

樹齢150年の大ケヤキに囲まれた「経堂の杜」。世田谷区の住宅地とは思えない豊かな緑が広がっている。
高性能化は必然の流れ。だが、「便利さ」だけでは暮らしは完結しない
マーケターとして、高性能住宅の普及や事業コンサルティングに関わっていた甲斐さん。スウェーデンで住宅と環境、コミュニティが調和している様子を目の当たりにして、「建物内部さえ快適にすればいい」といった価値観が大きく変わったと話す。
一方、日本では住宅の高性能化が進み、建物内部の快適性はますます向上している。2025年4月からの新築住宅の省エネ基準適合義務化も、この流れを後押ししている。
住宅の高性能化は必然の流れではあるが、「性能数値を比較し合うコモディティ化競争」が起きている現状に、別の視点が必要だというのが、甲斐さんの指摘だ。
甲斐さん: 大手ハウスメーカーやデベロッパーが住宅の高性能化を牽引していることもあって、現在住宅市場で主流となっている住まいは非常に高性能になり、その完成度は日増しに上がっていると感じています。この流れに乗らなければ企業として生き残れない……そんな構図が生まれていて、業界全体で性能数値を比較し合うコモディティ化が起きていると感じています。

甲斐さんは「住宅の快適性が上がることはもちろん大事」と前置きをした上で、「建物のみにフォーカスしていると、豊かな外環境が失われまちなみが無機質化し、住民の孤独化が引き起こされる可能性がある」と指摘する。
甲斐さん: 住宅が高性能化し快適性が高まるほど、基本的に暮らしは外部環境には依存しなくなります。暑くても、寒くても、強風が吹いても、家のなかに入ってしまえば問題なく過ごせるのですから、外部と関わる必要がなくなり、人は家から出なくなります。外部に関心が向かなくなれば、その住宅が集まった地域には人との関わりも生まれなくなり、コミュニティ形成は難しくなります。
では、自然環境や人と関わりながら豊かな暮らしをするためには、便利さを手放し、時代を巻き戻した暮らしをしなければならないのだろうか。
甲斐さん: 現代社会において、便利さを否定するという選択肢はありません。不便な住宅にお金を払いたいと思うユーザーはいないでしょう。ですから、これからの時代は、便利な技術を住宅に取り入れながら、外部環境との関係性によって生み出される豊かさをどう提案できるかが、非常に重要になります。
「関係性」はなぜ失われたのか? かつての「不便さ」が育んだ価値

写真提供:甲斐さん
甲斐さん: これは、沖縄にある集落の事例です。昔は、海風や台風から守るために、住宅を屋敷林で囲うのが一般的でした。まだ住宅性能が高くなかったので、屋敷林がないと暮らしが成り立たなかったのです。
屋敷林はそれぞれの家で管理していますが、きれいに保つためには隣の家との連携も必要になります。人々は自分の生活のために互いに協力し合って屋敷林を手入れし、暮らしていた。こうして地域全体に緑豊かなまちなみが育まれていったのです。
ただ、沖縄では1960年代から住宅のコンクリート化が進み、風に強い住まいが増えていったため、屋敷林は必要なくなっていきました。家に入り、外部のエネルギーを使ったエアコンをつけてしまえば快適な生活が送れるので、暮らしはそこで自己完結してしまう。便利さを手に入れた代わりに、自然環境や人々とのつながりは失われ、まちなみからも緑がなくなり、無機質になってしまったと言えます。
また、甲斐さんは、住宅に限らず、生活が便利になったことによって「人とのつながり=関係」が省かれていっていると分析する。
甲斐さん: 例えば、食事を例に考えてみます。昔は、大家族で食卓を囲んだり、茶の間で団らんの時間を持つのが一般的でした。今は、ファストフード店に行けば、誰とも関わらずに一人で食事をすることができます。
調理技術が発達していない時代まで遡れば、薪で火を起こしたり、かまどで調理をしたりと、食事を作って食べることは簡単ではありませんでした。互いに協力し合って食事を作り、全員が決まった時間に集まって食事を取る。簡単に食事が食べられない不便さを「人」の関係で補っていたため、それが自然と団らんの時間につながっていました。
一方、今はスイッチひとつ押せば、温かくて美味しいものが食べられる時代です。調理技術が進化し、好きなものを好きなタイミングで食べられるようになりましたし、ファストフード店では隣で食べている人とコミュニケーションを取る必要もありません。他人に左右されず、人に気を遣わなくても欲しいものが手に入れられる。つまり、便利さは人との「関係」を省いたと言えます。
以前は、人と関わりを持って生活をするのが当たり前で、「人付き合いが面倒だ」と考える余地もありませんでした。ただ、暮らしがどんどん便利になり、他者と関わりを持たずに生活ができる現代社会においては、「人と関わることは煩わしい」といった価値観を多くの人が持っています。

では、甲斐さんが考える「便利さ」と「不便」が、住宅や暮らし、コミュニティにどんな影響を与えているか、あらためて整理していこう。
住宅が「便利」であれば、暮らしは家の中で自己完結できる。手間のかかる緑の世話もしなくていいし、地域の人と関わることもなく気楽に暮らせる。ただ、周辺の自然環境と切り離された「閉じた住まい」ばかりが増えると、コミュニティは減少し、まちなみは無機質化する。
一方で、住宅が「不便」であれば、外部環境や人とつながっていないと暮らしは成り立たない。先ほど例に上がった屋敷林のように、緑の手入れも地域全体で取り組むことになる。個々の暮らしが住宅のなかで閉じないことで、地域全体が暮らしの場として機能するようになり、「美しいまちなみが自然と形成されていく」と甲斐さんは話す。
甲斐さん: 住宅性能が高くない時代は、あくまで「自分のため」に屋敷林を植えて、暮らしを成り立たせているわけです。隣の家も同じような考えで屋敷林を植えていて、ときには協力し合って手入れをします。その関わり合いが地域全体で繰り返されたことで、昔の集落のまちなみは美しく形成されていきました。これは、化学や生物学の分野の「自己組織化」と同じ現象です。誰かが指示したり、管理したりしなくても、それぞれが周りを見て動くことで、全体がバランス良く整っていくのです。

昔は、さまざまなことが「不便」だったゆえに、人々が力を合わせて住まいを守り、暮らしを成り立たせてきた。その営みから美しいまちなみやコミュニティが生まれていたのだが、現代は住環境も、人々の関係性も大きく変わってしまっている。では、これからの時代、豊かな自然環境を残しながら、地域の住人同士の関係を再生させていくためにはどうしたらいいのだろうか。
甲斐さん: 私は、これからの時代こそ、「関係を生かす」ことが大事だと考えています。住宅が高性能化して家の中だけで便利に暮らせるようになっても、暮らしが家のなかだけで完結しない、外に開かれたものになることで、暮らしはもっと豊かになると思います。

「経堂の杜」の室内から望む風景。豊かな緑に囲まれ、室内にいながらも心地良さを感じることができる。風景で外部環境とつながっている、これもまた自然との「関係」が生きていると言えるだろう。
主体的に関わりたくなる環境づくりが、これからの暮らしの豊かさをつくる
気候変動の影響や脱炭素社会の実現を考えても、住宅の高性能化は今後も欠かせない取り組みと言える。便利で快適な暮らしに対して、「関係が生む豊かさ」を組み合わせたハイブリッドな住まいが今後は求められていくだろう。今回甲斐さんがプロデュースしている「ケヤキファミリア」は、まさにそれを体現したプロジェクトだ。

「ケヤキファミリア」は、「自然に還るように、暮らす。」をコンセプトに掲げたコミュニティ型高性能賃貸住宅の建設プロジェクトだ。埼玉県新座市で代々土地を受け継いできた地主一家の敷地に賃貸住宅をつくり、コンセプトに共感した住まい手とともに、この土地の豊かさを分かち合おうという構想だ。
「ケヤキファミリア」には、大きな特徴がふたつある。ひとつは、賃貸ながら入居者自らがプランづくりに参加できることだ。建物の着工前に住まい手を募集(※)し、あらかじめ用意された基本プランをもとに、打ち合わせを重ねながら自分らしい住まいへと手を加えていくことができる。さらに、オーナーの承諾を得ていれば、退去時に現状復帰をする義務もない。
もうひとつは、「ケヤキファミリア」の敷地内に、入居者が利用できる菜園・コモンガーデン・コモンハウスが設けられている点だ。自然環境やコモンスペースの共有によって入居者同士が無理なくつながり、心地よい関係性を育んでいける仕掛けがあちこちに散りばめられている。同じ敷地内の母屋に暮らす地主や入居者同士のプライバシー空間もしっかり確保できるように木々や建物も配置される計画だ。
(※)2025年11月現在、すべての住戸が入居申込済みのため、募集を終了しています。
このプロジェクトは、地主一家が「この自然豊かな環境をどのように次の世代に残していくか」と考え、チームネットの甲斐さんに土地活用の相談を持ちかけたことが発端だったという。
甲斐さん: 最初に地主さんご一家にお会いしたとき、まず話に上がったのは、「どういった土地活用をすれば、この環境が活かせますか」という内容でした。コミュニティを育むきっかけになるブックカフェ、子育て世代を応援する保育園、地域の人のためになる医療施設……と、ご家族でさまざまな構想を練ってらっしゃったんです。
ただ、私は「その案は一旦横に置いておきましょう」とお話しさせていただきました。地域のための土地活用も素晴らしいことです。ただ、長年にわたって土地を守り続けてきた地主さん自身がもっと豊かになれる環境、素敵に暮らせるような世界観をまず一緒に考えてみたいと、提案させていただいたんです。

甲斐さん: いろいろとお話を伺った上で、「自然豊かな環境に住むためにお金を出してもらい、住まい手にも環境を育てることに関わってもらいましょう、この想いに共感できる仲間を集めましょう」と私は提案しました。地主さんたちの豊かな暮らしをさらに拡張し、「おすそ分け」するような発想に切り替え、地主さん自身の幸せも大事にできるようにしたのです。
地主さんたちの暮らしぶりを見れば、「ここに関わりたい」と思う人たちがきっと集まってくると思っていましたし、人が集まってくるのであれば、必然的にこのプロジェクトはよい結果を生むと感じていました。
「どんな事業をやって人を呼ぶか」ではなく、「自分たちの暮らしの豊かさをおすそ分けする仲間を集める」発想で事業を組み立てたらどうか。この提案を受けた瞬間、「地主さんご一家それぞれにスイッチが入ったと感じた」と甲斐さんは振り返る。
甲斐さん: 今回のプロジェクトの場合、地主さんご一家には3名のキーパーソンがいました。長年にわたって土地を受け継いできたご当主と、庭の手入れや草花の世話をしてきた奥様、独立して家を出ているご子息です。ご子息はコロナ禍を経て、この土地にある自然環境の魅力を再確認し、週末には家族を連れて戻ってくる生活を続けていらっしゃいました。
私が大事にしたのは、地主さんご一家の生き方や価値観を徹底的になぞり、それぞれが主体的に関わっていける未来のストーリーを描くことでした。それぞれの豊かな暮らしをどうやって創り上げていくかを考えた先に、賃貸住宅事業があったんです。

甲斐さん: 例えば、ご子息には敷地内に週末を過ごすゲストハウスを、奥様には今ある庭をさらに豊かにしたアウトドアリビングを設けることを提案に盛り込みました。ご当主は、ご子息が定期的に地元に戻ってきてくれて、主体的に関わってくれることを喜んでいました。
「ケヤキファミリア」は、入居者だけではなく、地主さん一家の暮らしもさらに豊かにし、入居者と恵みを分け合う場所です。不動産会社や開発業者に任せっきりにするのではなく、地主さんが「自分事」として主体的に関わっていく新しい賃貸経営の形だと考えています。
地主さんを「お客様」ではなく「事業主」であるととらえてみてください。土地と歴史を守ってきた地主さんだからこそできる事業が必ずあるはずです。その事業を一緒につくり上げ、地域の価値を高めていくことに、私は大きな可能性を感じています。

「ケヤキファミリア」の賃貸住宅は、全棟断熱等級6を実現するなど、高性能住宅としての要件を十分に満たしており、「便利」で快適に暮らせる機能性を備えている。ただ、便利さはあったとしても、住宅のなかに暮らしが閉じないような工夫が凝らされている。
手間暇かけて育まれた緑は、目にするだけでも心が癒され、思わず外に出たくなる。家から一歩踏み出すと、大ケヤキの木陰の下で読書を楽しんだり、共有の農園で野菜を育てて収穫したり、オープンスペースでのびのびと子どもを遊ばせたりと、入居者が主体的に環境や人に関わっていける空間が広がっている。
まさに「ケヤキファミリア」は、「便利さ」を否定せず、自然や人との「関係」が生み出す豊かさを組み合わせた実例だ。これこそが、チームネットが提案するこれからの「豊かさ」ひとつの解と言えるだろう。

ケヤキファミリアの中庭(2025年7月当時の様子)
個人では得るのが難しい贅沢な価値も、目的を同じくした仲間と力を合わせれば実現することができる。そんな「コミュニティ・ベネフィット」の発想を実装していくためには、コミュニティを機能させると、どんなベネフィットが得られるかを明確にすることが重要なポイントだ。
地主をはじめ、そこに住まう人それぞれが共有したいと思えるもの、主体的に関わり続けたいと思える外部環境が整っていれば、自然と人は集まり、同じ価値観を持った者同士の良好なコミュニティが生まれ、暮らしは豊かになっていく。その上で、高性能住宅から得られる便利さも存分に享受していけばいい。
「自然を残したいけれど緑の世話が大変」「地域の空き家を活用したい」など、地主や地方自治体が抱える課題と想いに向き合い、そこにある価値を再構築し、経営資源として事業を起こす。課題が価値になり、新たな景色が生まれ、人も集まり、人と人のつながりが再生する――チームネットが手がける住まいやまちには、そんな可能性で溢れている。「コミュニティ・ベネフィット」によって生み出された外部環境を守るため、人が主体的に関わり続ければ、きっとその先には美しいまちなみが連なっているに違いない。
| URL | https://www.teamnet.co.jp/ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役会長 甲斐徹郎 |
| 設立 | 1995年 |
| 本社 | 東京都世田谷区代田5-35-26(下北沢オフィス) |